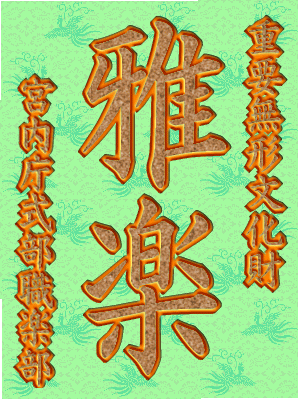 越殿楽残楽三返 えてんらくのこりがくさんべん
越殿楽残楽三返 えてんらくのこりがくさんべん重要無形文化財 雅楽 宮内庁式部職楽部 第3巻
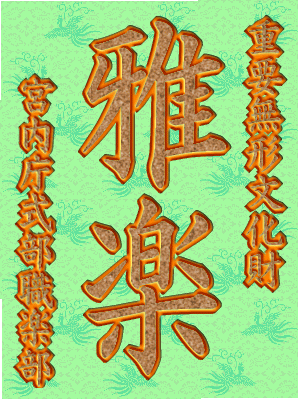 越殿楽残楽三返 えてんらくのこりがくさんべん
越殿楽残楽三返 えてんらくのこりがくさんべん
重要無形文化財 雅楽 宮内庁式部職楽部 第3巻


三調の「越殿楽」、残楽の粋と妙をじっくり鑑賞
管絃(かんげん)は平安朝の御遊(ぎょゆう)に由来する器楽合奏です。舞台上では前列に、打ち物〔打楽器:鞨鼓(かっこ)・楽太鼓(がくだいこ)・鉦鼓(しょうこ)〕、ついで弾き物〔絃楽器=楽琵琶(がくびわ)・楽箏(がくそう)〕、最後列に吹き物〔管楽器=笙(しょう)・篳篥・龍笛〕が並びます。(それぞれ向かって右から左に)
管絃の代表的な曲目「越殿楽」の管絃の粋を味わっていただくため、渡物(わたしもの 一種の移調)による平調(ひょうじょう)・黄鐘調(おうしきちょう)・盤渉調(ばんしきちょう)の三調の「越殿楽」を、次第に楽器を減らしてゆく残楽(のこりがく)という演出により収録しています。
渡物の背景には平安貴族の四季と調子を結びつけた観念があり、残楽は各楽器、なかでも箏の演奏技法を賞でる変奏法で、御遊の中から発展したと考えられている様式です。曲に先だち、各調の雰囲気を醸しだす短い音取(ねとり)が演奏されます。
(41分)
掲載開始 1999.03.15.
最終更新 2000.04.17.
wall paper courtesy of
![]()