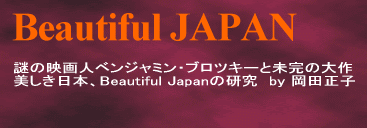
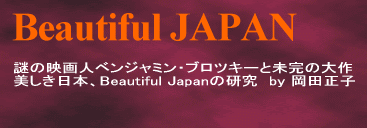
4.新大陸で新生活
ニューヨークに着いた身寄りのない、しかも身分を証明する一枚の書類すら持たない若者が一番馴染みやすかったのは、興行界をおいてなかったのかも知れません。密入国後の数年間、無国籍の青年はサーカスの一団の中に身を隠し、息を潜めていました。「ロシアの村での子供サーカス団を組織したことがある」という話は本当かも知れませんが、フィクションの可能性もなきにしもあらずです。しかしともかく、サーカスは彼の性にあっていました。彼が中国で製作したドキュメンタリー『A
TRIP THROUGH CHINA(中国)』14)でも、その後日本で撮影した『BEAUTIFUL
JAPAN』でも、彼は選んでサーカスおよび興行の世界を記録しています。
彼にとってサーカスは、生きるための糧を与えてくれた場所でもあり、それより何より一番大変なときに安全を確保してくれた「隠れ蓑」のようなところであり、アメリカとアメリカ文化のABCを覚えるための学校であり、それでいて冒険好きの青年を飽きさせないワクワクするものが存在している場所でもあったのでしょう。
『BEAUTIFUL JAPAN』では、火渡り興行をも記録していますが、一見して興行師の興行に見える火渡り、刃渡りの場面に、彼はあたかもそれが神道修験者の修行の図であるかのようなタイトルとコメントを付けています。こういった点がいかにもブロツキーらしいのではないかと想像します。また一方、そうした点が、後に真剣に日本紹介映画の製作をしているつもりであった日本側関係者をして苦々しく思わしめ、編集からブロツキーを外すべきだと結論づけさせるに至った点であったかも知れません。しかし、彼は愛すべき興行の世界の、少々いかがわしい部分こそが自分の身を救ったことを生涯忘れることはなく、中国においても、また日本においてもこうした興業の世界にどうしてもカメラの焦点が吸い寄せられるように行ってしまったのではないでしょうか。
アメリカでの以後の生活についても、まだ本人の陳述を確認するには至っていません。ただ、当時、アメリカにヨーロッパからの移民が大挙して押し掛け、言葉さえ不自由な低賃金労働者が急激に増えたという状況があったことを明記しておきたいと思います。ブロツキー自身の陳述によると、興行界を面白いようにスイスイ渡り歩いたようにいっており、少々眉唾かとも思えますが、言葉が不自由な低賃金労働者にとって、ブロツキーが係わったサーカス、コメディーっぽいミュージカル、ニッケルオデオンと呼ばれる5セントで映画を見ることができる映画小屋での映画鑑賞等は手頃な娯楽であり、こうした新来の移民たちには結構はやったということです。
この時代の映画についていえば、もちろんサイレントなわけですから、小難しい言葉を知らなくても内容が分かるような画面であるわけで、こうした人々にとってこの類の娯楽に接することは心から楽しめる貴重な機会だったに違いありません。また、映画界にはこれ以後も作り手の中にユダヤ人が多いというのも、元々ユダヤ人に優れた芸術的才能を持つ人が多いということはあるかもしれませんが、ブロツキー等作る側に回った人々にとっても、言葉の障害を越えて表現できる魅力的かつ格好な職業であったに違いないのです。
サーカス団の共同経営者になってからアメリカ国籍を取得し、それから英会話術を磨くため大学教官を雇い、故郷に錦を飾ることを目論んでみましたがそれは政治情勢が許さず、折角オデッサの港に上陸したところ兵隊に囲まれ拘留されそうになって、慌てて同行のアメリカ人学者に抗議してもらいほうほうの体でアメリカに戻りました。アメリカに帰国後、今度はミュージカル劇団を抱えて国内巡業をしたと本人はいっています。この部分は年号が不明ですが、共同でミュージカルを演出したクラークという男性の存在があり、また名の通った作品を作ったといっているところから、調査したら分かってくることもあるかも知れませんが、今のところ詳細は分かっていません。
西海岸に移ってから、せっかく建てた劇場を手放しカナダに行ってサーカス団を買収し、そのサーカス団を引き連れて中国で巡業を行ったというのは、何とも唐突な感じがします。中国でブロツキーを誘う動きがあったのか今のところ分からないからです。台湾でブロツキーのことを調べている『中国時報』の張記者は、船乗り時代に中国人の友人がいたのだろう見ていますが、現在確認されているわけではありません。結局、その時の中国巡業は天候不順でお客が集まらず失敗に終わり、さりとて連れていったサーカス団に給料を支払わないわけにもいかず、丁度入手した英国の友人の遺産が入らなければ彼は一文無しになっていたかもしれません。遺産を残してくれた友人というのは、ブロツキーが最初にオデッサ港で密航した英国船に乗っていた船乗り仲間のイギリス人G.ターウェイで、その後サーカスに潜り込んで小金を貯めたブロツキーがみせた好意を多として遺言状にブロツキーの名を書いておいてくれたのです。
遺産を受け取ってマニラにわたり、ここで貿易商のようなことをして小金を貯め、アメリカに戻りました。その際、船で同乗したお金持ちのアメリカ娘を見初め、サンフランシスコに戻ったところで結婚し少しの間は同国にとどまります。しかし、新婚早々慣れない定着生活にはすぐに飽きてしまったという理由で、今度は大量の米を持参して再び中国に渡ります。この時に新妻を同伴したかどうかは分かっていません。その後中国で牛肉を買って日露戦争中のロシアに売りに行ったといっているところなどから単独行動だった公算が大きいと思います。この商売は大当たりし、中国に戻って今度は生糸を買ってアメリカに戻ります。
このまま順調に貿易商の仕事が上手くいっていれば、彼が日本紹介映画を作ることはなかったでしょう。しかし、サンフランシスコに戻ったところで大地震に会い、財産を一切失ってしまったブロツキーは、周囲を見回し被災地に見物人が集まるのを見ると、早速喫茶店を開きます。そしてその次には同地に「5セント映画館」ニッケル・オデオンを開き、支店を持つまでになります。当時、雨後の竹の子のように同様の映画館が建ち、この世界の競争も激しいとみるとすぐに方向転換を考えますが、その時にまた中国に行こうと思い至ったのが何故なのか理由は分かりません。ニューヨークまで出かけて行って映画プリントと映画上映機器を買い揃え、上海に向かっています。
その後しばらくの間、ブロツキーの本拠地はアジアに移りますが、仕事柄からアメリカには度々戻ることになります。前述のフィルム・ライブラリー協議会「日本映画史素稿 8、 資料 帰山教正とトーマス栗原の業績」の中で執筆者金指氏は、第1次世界大戦中のブロツキーについて
「その折りにアメリカで映画制作を、それも東洋とくに日本を舞台にした作品を計画していたのが、トーマス・H・インスの所にいたベンジャミン・ブロドフスキーという人物で第1次大戦後の日本の発展に注目していた。そして東洋フィルム会社という会社を作り、同じくトーマス・H・インスの傘下にいたトーマス栗原と意気投合しての会社で日本紹介の劇映画を作る計画をしていた。」と述べています。
金指氏が何をもとに書かれたのか分かりませんし、はっきりとした年月日、細かい事情なども記されていないのは残念です。その時期を漠然と「第1次世界大戦の後」と述べておられる点は、以下の事実を考えると真実とは思えません。ここに出てくるトーマス・H・インスとは、1910年代アメリカ映画史では「イントレランス」の製作、監督で知られるグリフィスと並んで活躍中の映画製作者、監督、俳優であった大物です。ブロツキーがアメリカの映画関係者、しかもインスのような大物と実際にどのような関係にあったかは不明です。「インスの所にいた」というと、いかにもインスの所で働いていたように聞こえますが、先に示した年表に見る限り、時間の経過から見てブロツキーにとって、それは無理ではないかと思われます。
ブロツキーは1913年横浜にヴァライエティー・フィRム・エクスチェンジ社の事務所を構えています。なるほど、この会社の実績などは今日分かりませんから、事務所を構えながらインスの処にいることはできないことはないでしょうが、それでも少々無理があるように思います。一方、東洋フィルム会社の設立の1917年に、トーマス栗原はロサンゼルス北サンペドロ街に設けた日本人活動写真俳優組合の評議員を引き受けたりしているところを見ると、この時点でブロツキーが栗原と手を組んで会社を組織したようには思えないのです。
翌1918年4月に既に撮影済みの『BEAUTIFUL
JAPAN』のフッテージ売り込みのためブロツキーが渡米した帰途、数人の日本人俳優を含む映画製作スタッフを連れて日本に戻るとき、栗原が同行しています。つまり、1917年にブロツキーは東洋フィルム会社を設立し、同年『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影済み映像の売り込みに渡米した際、その交渉先、相談先の一つがインスであったのではないでしょうか。
インスのもとに映画人として実績を積んでいたトーマス栗原、早川雪洲をはじめ沢山の日本人映画人が育っていました。ブロツキーは、「日本国は日本を紹介するような映像を今後も望んでいるようだから、それを我が東洋フィルム会社で作っていこうと思う」というようなことをいってインスの周辺にいた日本人映画人の間に同志を募り、その中にトーマス栗原がいたということではないでしょうか。
そして、翌年ブロツキーが渡米したその帰途、既に日本に帰って仕事をする決断を固めたトーマス栗原等がブロツキーに同行し、帰国後早速計画を実行に移したのです。この時に帰国したアメリカ帰りの日本人俳優が横浜で新聞社のインタビューに答えて東洋フィルム会社が計画中の劇映画つくりについて具体的なプランを述べています。
「日本紹介映画は何も日本のドキュメンタリーでなくともよい、むしろ日本伝統文化を外国人に理解してもらいやすい文芸時代劇映画でこそ、真の日本を紹介できるのだ」というようなことを後に栗原が語っているところを見ると、この主題についてはブロツキーと栗原の間では議論をしつくしていたようです。先の新聞インタビューを読む限り、この時点で『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影は終了しかけているように聞こえるのですが、東洋フィルム会社はその後も横浜元街小学校に運動会を撮り足しに行くなど、実際には『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影は1918年10月まで継続していました。同年11月、撮り足した『BEAUTIFUL
JAPAN』と東洋フィルム会社として製作した劇映画2本(『成金』『東洋の夢』)とを持ち、ブロツキーはトーマス栗原、尾関を伴って再びアメリカを目指します。しかし、中国で撮影した『A
TRIP THROUGH CHINA』の時のようにアメリカの映画市場に東洋フィルム会社の日本の映像は売れることはありませんでした。
アメリカ映画史を研究対象とされている日本人映画史研究者で、グリフィス、インス等の時代を調査されている方は、早川雪洲、トーマス栗原等についても研究されていると思いますが、日本の映画史、特にドキュメンタリー史に残っているブロツキーの足跡にも注目して研究されるよう期待します。インスの直接の指導を受けたトーマス栗原は、インスの周りにいた日本人の中でも優秀だったからでしょうか、インスから「トーマス」という名を貰ったそうですが、彼の実績は日本でも早くから理解され、帰国してから劇映画の監督を任され、俳優の養成にも努めたことで大きく評価され、日本映画史にその名を残しています。
彼が監督をした劇映画およびドキュメンタリー作品は、ほとんどが通称「大活」と呼ばれた大正活映時代に作りましたが、彼が日本で初めて監督として関与した映画作品は上記に示すようにブロツキーが支配人をしていた東洋フィルム会社の劇映画『成金』と『東洋の夢』の2本と『美しき日本』と題する『BEAUTIFUL
JAPAN』日本版です。
残念ながら現在トーマス栗原の作品で見つかっているのは『後藤三次』という劇映画一本だということを国立近代美術館フィルムセンターの入江良郎氏に教えていただきました。トーマス栗原については別の項でもう少し詳しく述べたいと思います。
ブロツキーは、当時としてはかなりフットワークが軽い人でアジアとアメリカを何度も往復しています。しかし、横浜の税関の入出国記録は関東大震災などの災害で全く残っていません。渡米の目的は、当初は主に東アジアで撮った映像を作品としてアメリカの映画興行界の市場の乗せることでした。しかし、『回顧録』にもある通り、東洋フィルム会社時代に日本紹介映画を作るに当たって一緒に日本で働くスタッフや、俳優との交渉にもわざわざアメリカに戻って面談の上決めており、さらにトーマス栗原と交渉した時には、新たに劇映画を本格的に作るための人材を探しています。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT