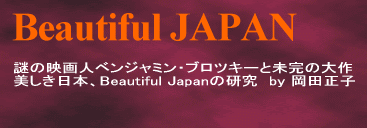
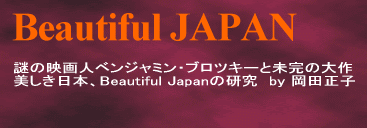
5.ブロツキーの見た中国
日本における映画の勃興期に重要な位置にいたブロツキーは、来日の前に活動していた中国の初期の映画界でも大きな役割を果たしています。中国に映像の導入が記されたは1896年です。中国無声映画の歴史については、先に紹介した中国電影出版社(北京)刊行の『中国無声電影史』に詳しいので、同書を参考にしていただきたいと思います。同書によると、当初は西欧の映画人が中国映画界を牛耳っていました。注目に値するのは、記録が記す限り、ブロツキー自身が意図したか否かに関わらず、中国人の最初の映画監督が生まれたのは彼が上海に設立したアジア影戯公司で製作した劇映画においてだということです。
また、彼が中国各地で撮影した最初のドキュメンタリー『A
TRIP THROUGH CHINA(中国)』は、現在見ることができませんのでどのような撮り方をしているか判りませんが、80有余年たった今となっては歴史的な価値のある作品に違いありません。中国でもアメリカでもそのプリントが見付かっておらず、残念ながら映像を見ることは不可能と思われてきましたが、今回の調査で『A
TRIP THROUGH CHINA』が台湾の国家電影資料館にビデオコピーの形で現存していることが分かったのは大きな収穫だったと思っています。まだ私どもの手元に映像は到着していませんが、現在日本でも見ることができるよう手配をお願いしているところです。作品の内容はアメリカで上映された際の新聞記録から下記のようなものであったことが既に分かっています。
『A TRIP THROUGH CHINA』全10巻。撮影10万フィートの内1万フィート分を作品として使った。
旅程は桑港、北京、香港、上海、杭州, 広東、天津、Soochow、無錫、南京、マカオ、漢江、九龍、アバディーン、ニューチュワンと某新聞記事にある。
内容:
中国人の生活、習慣、衣装及び信仰。工業。スポーツ、労働、荷物の運送(運河航行舟、駱駝・驢馬に荷物を乗せ移動、荷車、人力車)、 港湾労働者、樵の仕事、大道芸、鵜飼い。公園、街中、大学、病院。盲聾唖学校。筍、竹の利用法。パゴダ、明時代の墓。水上生活者と台風の被害。浮浪児。広東の婚儀、葬儀。家の守り神信仰。北京:紫禁城、清皇帝の一族、兵隊、競馬。YMCAが行った3万5千人の人々による大運動会、万里の長城とその他の重要都市の要塞、濠
映画の関係者としてブロツキーが中国に滞在したのは僅かに5,6年、日本に滞在したのも6,7年くらいだったことを考えると、本人が意図したわけではない大きな成果が両国の映画界において築かれ、7,80年たった今日振り返ると、ブロツキーは中国の、あるいは日本の映画界に結果的に転機をもたらしていたのです。
しかし、その活躍とは反比例するかのように彼自身の存在は大方無視され、評価は決して高くなりませんでした。映画人としての彼には斯くとした理念があったわけではなく、ただ時代の風に乗ってアメリカ大陸で、中国で、日本で映画と関わりを持ち、各々の地で向かえるべくして映像の転機を行き会ってしまった感があります。そうした状況の中でも、例えば彼に白人優位の優越意識などがなかったところから、彼に転機を呼ぶ役割が与えられたという面もあったのかも知れません。
『中国無声電影史』の中でブロツキーについて記述している箇所を引用してみましょう。先に述べましたように、この部分は本人がサンフランシスコの裁判所で陳述した英文の記録を基に、史実と照らし合わせ、どうも彼が述べていることはおかしいとしている部分は省いたり、あるいは原文を読んだ人がおかしいとした箇所でも可能性としてはあり得る部分はそのように記述したりしていて、資料として信用できるような気がします。
1909年、上海に東洋映画社(チャイナ・フィルム・プレス社の英文記事ではアジア・フィルム・カンパニーとされている)が創設された。これは、最も初期に中国に設立された映画会社でアメリカ人ベンジャミン・ブロツキーが興したものである。(中略)(この頃からブロツキーは)以前よりよく知っていた中国も訪れるようになった。サーカス興業を中国で行った後、アメリカ、ロシア、中国の3国間をたびたび往復している。(アメリカ国内では)サンフランシスコに劇場を建てたのを皮切りに、ポートランド、シアトルその他の地域に支店を設けた。その内に国内での仕事の競合が激化すると、映画の興行権を買い付け、映写機器をニューヨークで買い揃え、再び中国に向かった。上海の香港第一街(上海市香港街1番地)に東洋映画社を設立した。上海で盛んに上映会を催し、アメリカから持ち込んだ映画の公開を行った。当初はお客を金を払って観覧者を募った。その内、観覧希望者がどんどん増え、大繁盛となった。
つぎに彼は自分でも映画を撮るようになった。『中国』という題名のドキュメンタリー作品をものし、北京で見たもの、観察したものの記録を製作した。紫禁城での撮影を許可された最初で最後の白人映像製作者であると言われている。前述の作品に紫禁城と夏の宮殿の風景が映し出される。袁世凱の住居、軍隊学校の行進も映っている。ということは『中国映像発達史』で著者は、「清政府の下で西太后の姿を映像に撮るなどということは誰にも不可能であった。」として、ブロツキーが西太后の姿を映像に残した筈はないとしたことは誤りかも知れない。ブロツキーは、上海ではなく北京で映像を作った。上海ではただ一本、『不運な子』という題名の劇映画を作ったが、その内容は不明である。短い説話に基づくものであろう。
ブロツキーは香港にも製作旅行を敢行している。その時に製作された作品の内の一つは『丸焼きアヒル泥棒』である。単純な筋立てで、金持ちの太った商人からこんがりと焼いたアヒルを盗んだ痩せ細った泥棒が警官に捕まえられると云うものである。梁少が監督兼主役の泥棒を演じた。(中略)梁は、中国で初めて監督としてその名が公開された中国人映画監督である。彼は香港の広東オペラ清平楽(清平楽とは、詩歌曲を作曲する場合に使われる音律で「歌と平和の音曲」の意味を持つ。)の一員で、『丸焼きアヒル泥棒』もおそらく広東オペラの演目であったのだろう。『土鍋で裁判を正す』は彼のもう一つの作品とされていた。しかし、この作品はこの頃作られたのではなく1913年の製作ということがその後判明している。
1912年、ブロツキーは東洋映画社の所有権をアメリカ製の映像機器とともに上海の南洋生命保険会社の支配人に譲った。ブロツキーの来歴、商売実績から推察するに、会社を手放すに至ったのは彼が商売に失敗したのではなかったろうと思われる。後に、彼自身が「中国ではこの頃、清政権打倒の動きが激しく、革命を呼びそうな勢いであった。外国人に対する反感も高まっていた。」といっている。彼が上映していた映画はアメリカで買い付けてきたものだった。西部劇の上映をしているとき、スクリーン上のカウボーイが“(観客の)中華国民に対して”ピストルを向けるだけでも、観客は反感をむき出しにした。人々は『白悪魔!』と口々に叫びながら劇場に火を放った。劇場の被害は上映を再開するには大きすぎた。当時の中国社会の歴史的状況からすると、ブロツキーの言葉もあながち信じられない話ではない。 中国無声電影史(中国電影出版社、1996年発行)より
1912年にあっさりと上海を離れたブロツキーが、次に現れたのは1913年の日本です。その頃の米国の新聞記事には「現在紐育にいる香港の中国映画社マネージャー、ブロツキー」15)として紹介されています。ともかく、彼に中国におけるドキュメンタリー映画の撮影・製作の経歴があり、アメリカ本国でこの中国で撮った映画が好評を得たという事実が認められたからこそ、日本政府の関係者も彼を映像製作者として認め、安心して撮影の後援を申し出たものと思われます。この歴史的に価値のある映像はぜひ見てみたいものです。
当初、日本国が日本紹介映画を外国映画人に作らせようとしていたことを知ったブロツキーが『A
TRIP THROUGH CHINA』の製作経験をもって自らを売り込んだ可能性もあると考えていました。というのも、横浜の事務所で準備万端整えていた1916年には、アメリカの各地で『A
TRIP THROUGH CHINA』が盛んに上映され、好評を博していたようだからです。しかし、ブロツキーが日本紹介映像を作ることになったきっかけについては、鉄道院、JTB等が日本紹介映画製作企画を立てた際、JTBの会員企業の経営者としてその動きのごく間近にいた日本人実業家浅野総一郎・良三父子がブロツキーに振り当てるように動いたという方が真実に近いようだということが分かってきました。
ブロツキーと浅野父子の関係については別項(「7.浅野総一郎、良三父子とブロツキー」)でもう少し詳しく触れてみたいと思います。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT