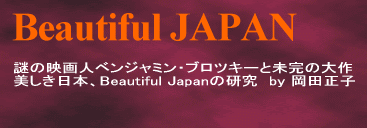
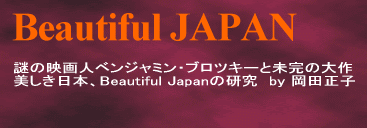
3.帝政ロシア時代のユダヤ人
ロシアのユダヤ人は19世紀後半から、国内の差別迫害から逃れるために、大勢が西ヨーロッパへ、そしてそこから大半が新大陸アメリカへと移住していきました。その数は1881年のポグロム‐集団組織的大虐殺、特にユダヤ人を対象にしたものを指すことが多い‐以降増加し、第一次大戦までに100万人以上に昇るとユダヤ人の問題を研究されている高尾千津子先生から伺いました。ブロツキーの生家の細かい事情は分かりませんが、ブロツキー自身は、ロシアに留まっていたら自分の将来はないと考えたといっています。
14歳の、教育もまともに受けていない少年は、たった一人で世界に飛び出しました。オデッサの港にたまたま停泊していた英国貨物船に密航しているところを見付かり、船長によってイスタンブールでトルコ警察に突き出され、言葉が全く通じなかったからでしょうか、同地駐在のロシア領事の事情徴収を受けることになりながら、策を弄してまんまと官憲の手から逃げ出し、領事との面会すら免れ、港の英国船に戻ったので、船長も呆れて再び官憲に突き出すこともせずに、船で下働きをさせた上、給料も与えたといいますから、何ともいい加減な気がしますが、ともかくブロツキー少年はイスタンブールの港からさらに広い世界へと脱出に成功し、言葉も通じず、知り合いとて一人もいない世界で生き抜くことになりました。
それ以後の足取りを見ていると、運にも恵まれたようですが、教育で培うことのできない智慧と日々鍛錬して手に入れた勘と機転が彼の人生を救いました。彼の語るところを全て信じる訳にはいきませんが、彼自身には特別な羅針盤が備わっており、その羅針盤が要所要所で取るべき道を指し示してくれたように見えます。
彼が南アフリカまで行ってしまった後、ヨーロッパに戻る際には船が難破するなどの困難にあいながら紆余曲折の末、到達して上陸したニューヨークの港には、当時、ヨーロッパからの移住者が大きな船から排出されていました。特にロシアは革命前夜でした。革命直後には大量のロシア人貴族が命辛々新大陸に辿り着いたのでしょうが、それ以前にロシア脱出を迫られたのはユダヤ人だったようです。
ブロツキーが育った帝政ロシア下のユダヤ人の村の様子は、日本人にも分かりやすい例としてはブロードウェイ・ミュージカルでお馴染みの『屋根の上のヴァイオリン弾き』13)の舞台になった村のようではなかったかと思います。『屋根の上…』は帝政ロシア末期のお話で、ウクライナの小さなユダヤ人村落から、迫害を受けた村人が結局全員退去をせざるを得なくなり、散り散りに去って行くという、エンターテイメントにはなりにくい悲惨な歴史的背景のもと、厳しい宗教的規律を守りつつ慎ましく暮らしていたユダヤ民族の物語なのです。ブロツキーが生まれ育った村テクタリンは、地図上どこに位置するのか確認がとれていませんが、少年が歩いてオデッサの港に辿り着けたことを考えると、この『屋根の上…』の背景になったウクライナの小さな村に似た場所ではないかと思うのですが、これは全くの推測に過ぎません。
ハリウッドで1972年に映画化された『屋根の上…』は、ウクライナに行って撮影できる時代ではなかったために、幾つかの撮影候補地の中から多くの亡命ユダヤ人に意見を聞いて、最も典型的なウクライナのユダヤ人村落に似た雰囲気を持った土地として、当時のユーゴスラビア、ザグレブ近郊の村が選ばれ、そこで撮影されたということです。
ロシアのユダヤ人に関する情報を取り扱っているサイトがインターネットには幾つかあります。その一つに「テクタリン」という地名について問い合わせを出したのですが、現在の処、返事を下さった方はありますが場所の特定はできていません。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT