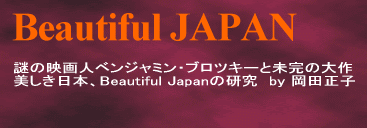
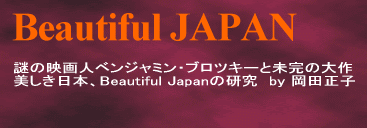
2.ベンジャミン・ブロツキーはアメリカ人?それともロシア人?
ベンジャミン・ブロツキーは、日本の映画史にも、米国の映画史にもその名を大きく留めているとはいえません。例えば、先に紹介した『回顧録』ではブロツキーの氏名すら記録されていません。その後、川崎市市民ミュージアムの学芸員濱崎好治氏の送ってくださった『キネマ旬報』8)1966年9月上旬号に掲載された田中純一郎氏による「連載 秘録日本映画」には米国籍を持つブロツキーを「ロシヤ人ブロドスキー」として紹介しています。国内の記録としてはこの他に「ブロドスキーの再来日」という記事を『横浜貿易新聞』9)大正7年4月3日付けに見つけましたが、列車まで提供した鉄道院など公的機関の記録としては資料が見つかっていません。1999年7月現在、国内で見つかった記事を総合すると「大正5年に横浜にスタジオを造り」、「大正6年10月に撮影のために男女の俳優を伴って来日」した「米国映画会社」の「ロシヤ人」が「大正7年4月1日」に撮影スタッフを連れて「再来日」したことになり、ますます矛盾と謎が広がってしまいました。
一方、米国でもブロツキーに関する記事がわずかながら見つかりました。そこで分かったことは、ブロツキーが来日する前の数年間、中国に滞在し、上海・香港に映画会社を設立し、中国各地でドキュメンタリーを撮り、撮影した記録を米国に持ち帰り、各地で上映講演会を催し好評を博したことです。残っている文書記録というのは、その際上映された作品に関する幾つかの新聞記事10)です。
ブロツキーに関して調査を進める内に、中国電影出版社(北京)が1996年に発行した『中国無声電影史』11)に行き当たりました。この本の存在は最初、米国ワシントン在住の日米経済史研究家エドワード・S・ミラー氏が英語抄訳を送付してくださり知ったのですが、それを読む内に自分では中国語は読めはしないものの、なぜかどうしても原文に接してみたくなり、ちょうど仕事で北京に出張する在京の友人、映像プロダクション株式会社龍影の李纓・張怡夫妻にお願いして同地で購入してきていただき、中国語の原著を入手しました。読んでみると、というよりは漢字を眼で追ってみると、英語の訳で読んでいた通り、ロシア生まれのブロツキーの来歴と、後に彼が訪れた無声映画導入直後の中国での彼の上海、香港に基盤をおいた活動の具体的な仕事の内容等が書かれているようでした。彼の現在分かっている来歴については、年表の形に置き換えて後述します(8-12頁)。
しかし、ひょっと脚注に目を向けてみると、たった一行ですが、英語訳では見当たらなかった記述がありました。それによると、「この(『中国無声電影史』におけるブロツキーに関する)記述は台湾の新聞『中国時報』12)1995年6月4日付けの記事に基づいて書かれた」とあったのです。同じ漢字を使う文化圏に住んでいることをこれほど嬉しく思ったことはありません。なぜなら中国語が全く判らないのに、書かれた内容がハッキリ判るのですから。早速同記事を入手しました。『中国時報』記者である執筆者張氏によると、『中国時報』の記事は「1900年代初頭にブロツキー自身が米国カリフォルニア州の裁判所で書記の助けを得て陳述記録した自分史の部分中国語訳である」とあります。またしても抄訳であることに焦燥の念を禁じ得ませんでしたが、気を取り直し、さっそく友人のパレッタ企画納村公子氏に中国語からの邦訳をお願いしました。
タブロイド版一頁分の紙面を埋め尽くしていたのは、ブロツキー本人が語る、少なくとも三つの大陸をまたいで繰り広げられる、スリル満点の冒険小説のような半生でした。一方的に本人が語った記述であるだけに、部分的にはかなりリアルであり、詳しいのですが、その一方で、少々眉唾な逸話も混じり、思わずミュンヒハウゼン物語のほら吹き男爵を思いだしてしまうような、面白すぎる内容です。
しかし、今から90年前に一人の少年が体験した物語の真偽は確かめられようなく、オーバーな表現、主観的な記述を現在の時点で確かめ、訂正することは不可能です。ともかく彼自身の陳述により、なぜ日本でブロツキーがある人には米国人、別の人にはロシア人と認識されたかなどを含む、彼の前半生の大筋が理解できるよう記述されています。なお現在、この『中国時報』で中国語抄訳のもととなったブロツキー本人の英文陳述記録を入手し分析をするつもりで、中国語抄訳執筆者張記者に連絡をとっていますが、未だ原文入手経路についてはっきりしたことが伺い出せず、原文入手に成功していないのは残念です。
現在までに国内外で見付かった幾つかの資料(『中国時報』、『中国無声電影史』、『ジャパン・ディレクトリー横浜版』、『キネマ旬報』、『活動倶楽部』、『活動雑誌』、『横浜貿易新報』、『サンフランシスコ・ディレクトリー(フランク・ブレン氏調査)』、米国新聞記事、その他雑誌・新聞記事)をもとに、以下に示すように彼の半生を年表にしてみました。現在の時点では、詳しい年号が付せられない項目が多くあり、これらについてはおいおい年号を埋めなければならない課題事項であることを思い起こすためにもそのままにしてあります。生誕より1912年までの事項については、現在、本人の申告のみしか材料がないのでそのままを記しましたが、一つ一つのできごとの真偽の是非は確認できないものが多いことを明記しておきます。中国における事項の一部は『中国無声電影史』において編集者の手により確認された事項が同書に転載されています(「5.ブロツキーの見た中国」参照)。
1875年 0歳
ロシア(ウクライナ?)の寒村テクタリンに、貧しいユダヤ人の家族の12人兄弟の一人として生まれた。少なくとも長男ではなかった。
1889年 14歳
母親が亡くなる。長男は奉公に出るが、彼は家から離れられなかった。村で子供同士でサーカス団のようなものを組織して、周囲を大いに沸かせるが、父親には渋い顔をされた。父親の命により鍛冶屋に奉公に出るが、親方が吝嗇であったため、身の回りのモノを麻袋に詰め、革の帽子とコートを身に着け逃げだし、オデッサ港を目指す。途中、ジプシーの一団から馬をかすめ取り、それを別のジプシーに売り飛ばすが、結局、袋叩きに合い、帽子とコートのみ手元に残る。
オデッサの港に停泊中の英国貨物船に無断で潜り込む。石炭箱に潜むが見つかり、イスタンブールで警察に突き出される。ロシア領事に事情を聞かれるが、危機一髪逃げおうせて英国貨物船に戻る。英国船では重宝な下働きとして何でもこなす。やがて仕事が認められ給料まで貰う。
英国到着時には機関士ジョージ・ターウェイと友達になっていた。この頃、給料をコートの裏に縫いつけることを思いつく。再船出。正式に石炭係の船員として契約。南アフリカで荷物積載後、英国への帰途、難破。仏汽船に救助される。
仏政府がブロツキーを遭難者として英国に送還。イギリスの港で待機していた友人G・ターウェイの機転で米国行きの船に乗る。8日後、ニューヨークに上陸。船員生活は終了。
上陸早々、サーカスの天幕を発見し、潜入。サーカス団で下働きをする。週給3ドル。サーカスのライオンの命を救う。クリスマス特別手当100ドルが支払われる。週給が50,60ドルに上がる。
サーカス団潜入後4年目、サーカス団が経営不振に陥いる。上着の裏に縫いつけて蓄えた9000ドルを差し出す。翌年のクリスマス特別手当1000ドル。同時に購買部、衣装部兼任マネージャーとなる。週給100ドルに上がる。氏名公開。サーカス団の共同経営者となる。米国籍を取得。
高価且つ目立つ服装を揃え、プリンストン大学に個人英語教授を捜しに行き、目当ての教務官に強引に頼み込むが、再三断られる。
6週間後、元プリンストン大学教務官の個人英語教授を伴い豪華客船で渡欧。英国に向かう。
友人G・ターウェイに再会。彼のため、土地購入、経済的援助、また総機関士となる手助けをする。
ロシア、オデッサに上陸。ロシア兵に拘禁されそうになったが、米人教授に助けられる。即刻ロシアを離れる。
帰米後、劇場で働く。偶然、音楽劇制作者クラーク某と知合い、2人でフィラデルフィアに劇場を開く。
2年後、2人で制作した20作品(「Peg O' My
Heart」「Glass House」等)を携えて米国各地を巡業。
サンフランシスコに劇場を建てる。その後、劇場を売り払い、カナダでサーカス団を買い、このサーカスを率いて中国へ渡るが、中国は雨期で 客の入は悪く、団員に給料を払わなければ成らず、四苦八苦する。
アメリカ大使館から旧友ターウェイ死亡の報と6万ドルの遺産が残されたことが通知される。渡英し遺産を受け取り帰米。帰途、徴兵されるも逃げ出す。
マニラに渡り、同地で商店を開業。相当利潤(75000ドル)を挙げ、その後、帰米。その船上で、未来の妻と知り合う。
サンフランシスコに新居を構える。
船一艘分の米を2万5千ドルで買い、中国に運び、それを35万ドルで売る。中国で牛肉を買い付け、日露戦争最中のロシアに運び一財産を築く。中国で生糸を買い付け帰米。
1906年 31歳
4月18日、アメリカ、カリフォルニア州に大地震が発生。サンフランシスコにあるニュー・ブランズウィック・ホテルに逗留中のブロツキー夫妻は救助されるが、生糸は灰塵と化した。
被災地サンフランシスコの街角にコーヒーショップを開店。サンフランシスコのマーケット街に「5セント映画館」を設立。ポートランドやシアトルにも拡大する勢い。
ニューヨークに行き、映画プリントと上映機器を購入し中国に向かう。カリフォルニアの裁判所で半生を記述。(経緯の詳細未だ不明)
1909年 34歳
アメリカ人として上海と香港(香港第一街)に「アジア影戯公司(別称、東洋映画社)」を設立。2カ所で同時に短編映画の撮影を開始。『不幸な子供』は上海で撮影。香港撮影作品は『アヒルの丸焼き泥棒』(香港初製作劇映画。監督兼主役を演じた梁少は、中国人最初の映画監督となる。)
1912年 37歳
上海の「アジア影戯公司」は経営不振に陥り、南洋生命保険会社の米国人経営者等に譲渡。
ブロツキーは、後に「中国ではこの頃、清政権打倒の動きが激しく、革
命の機運が見え、反欧米人感情も高まっていた。」と云っている。上映
していた米国製西部劇の上映中、銀幕上のカウボーイが手前にピストルを向けるだけで観客は反感をむき出しにし『白悪魔!』と叫んで、挙げ句の果てに劇場に火を放った。劇場の被害は甚大だった。
ブロツキーに関する新聞報道を見て、旧友(中国政府顧問。袁世凱子息か?父親は清朝廷で軍のトップとの記述がある。)が訪ね、ブロツキーに25年間の映画配給独占権を許可した。
ブロツキーの中国初製作長編ドキュメンタリー『中国(A
TRIP THROUGH CHINA)』が6ヶ月上映され、翌年中国の主要都市の82劇場で上映された。
他国大使が独占権を妬んだため、ブロツキーは国際的企業を組織した。孫文の計らいで(?)中国政府の同意を得、会社を中国人に譲り渡すことにし、この取引により300万元を得、帰米。
この頃、浅野良三と知り合う。(未確認)
1913年
横浜山下町72番地にヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ社を創設、総支配人となる。支配人はC.H.プール。本社をサンフランシスコとし、シネマトグラフ・フィルム配給と映像機器販売を行う会社として登録する。
1914年
ヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ社支配人がC.H.ブレドフに代わる。
1915年
ヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ社を山下町56番地に移す。支配人の記述が無くなる。
1916年 41歳
8月11日VARIETY誌 「現在紐育にいる香港の中国映画社マネージャーのブロツキー」として記事が紹介される。リアルト劇場の支配人ロザフェルに『A
TRIP THROUGH CHINA』を見せたとある。
1917年 42歳
3月17日Moving Picture News紙他数紙誌に『A
TRIP THROUGH CHINA』上映記事掲載さる。アメリカ各地(カリフォルニア、アリゾナ、ネヴァダ等々)で同作品の上映が相次ぐ。デイビス兄弟社が興行元。
10月、この頃ローランド・モリスが駐日大使として日本に赴任。
日本政府の委託を受け、東京映画会社と合作で米中の人々が日本に対する理解を深めることを目的とした映画の制作にかかる。
10月14日、元街小学校運動会風景を横浜公園で撮影。「米国官憲の命で」という名目の下。
10月24日、箱根の撮影。スタッフ25名。(東北・関西の撮影一部完了)
この年のジャパン・ディレクトリー横浜版にはブロツキーとその会社に関する記述がない。
サンフランシスコにおけるブロツキーの住所はヴァン・ネス街840番地
1918年 43歳
社名を変更し、東洋フィルム会社とする。ブロツキーは同社の支配人として登録する。住所も山下町31番地に移動。
1月6日、上野不忍池端で出初式挙行。この式典の詳細が映像に収まるも撮影はブロツキーが立ち会ったか確認不可。ブロツキー再来日の記事と 日程的に矛盾するかどうか、ギリギリの線。
4月3日、東洋汽船の船で再来日。この頃、横浜元町に撮影所を開設。フランス人アルフレッド・ジェラールによって建てられたレンガ工場の跡地に建てたもの。
10月17日、元街小学校運動会風景を横浜公園で撮影。
11月25日、サイベリア丸で横浜を出航、渡米。
サンフランシスコにおけるブロツキーの住所はクレイトン206番地に変わる。
1919年 44歳
劇映画『成金』『東洋の夢』を製作。春、撮った映像を携えて渡米。トーマス・栗原、尾崎庄太郎(美術)等同行す。(帰国は4月10日とあるが、米国滞在は春から3ヶ月ともある。)
『BEAUTIFUL JAPAN』の仕上げ作業からブロツキーは外されることになり、米国内での営業を担当しろといわれ、話し合うが、結局決裂。
ジャパン・ディレクトリーに登録している社名が変更され、東洋フィルム・フィーチャーとなる。(支配人名記載無し)
サンフランシスコ市のディレクトリーによるとこの年サンライズ・フィルム株式会社(ゴールデンゲート街100番地)の社員となったことになっている。
1920年 45歳
4月、東洋フィルム会社の全ての権利を、機材込みで浅野良三に譲渡。浅野は、新会社に大正活映と銘々。しかし、ジャパン・ディレクトリーに登録している社名は東洋フィルム・フィーチャーのまま。
サンフランシスコにおけるブロツキーの住所はクレイトン街であり、この住所に1923年までは住んでいることが確認できた。
また、21年のディレクトリーではサンライズ・フィルムの支配人とされており、マミーという夫人があると記述がある。
12月23日、大正活映はトーマス栗原が監督した『美しき日本』を浅草千代田館で発表。
後半生は株の売買、金鉱探査を行い、不動産・貿易業に携わり、新聞社(サンタ・モニカ・ニューズ)を経営したこともある。
日本では、ブロツキーはある時にはロシア人と呼ばれ、またある時にはアメリカ人と認められて暮らしていました。本人にアメリカ人になった自覚はあっても、元プリンストン大学教務官の個人授業がどのくらい功を奏したか分かりませんが、実際には英語を自由自在に使いこなすまでには至っておらず、英語に不慣れな日本人から見ても、どうもおかしな英語を操る外国人に見えたのかも知れません。あるいは、アメリカ人としての習慣も身に付いていなかったかも知れません。
もっとも、それでしおたれてしまう男ではなかったようです。一つ処に定住したことのないブロツキーは、結局、故郷を持たないコスモポリタンとして、気ままに人生の舵を取りながら他人には考えられないような航路を辿って暮らしたようです。仕事の上でも、家庭的にも一つの仕事、一人の伴侶を守り抜くつもりは始めから毛頭ないように見え、むしろ意図的に慣れた事業、築き上げた人間関係を数年もすると切り離して、後腐れを振り払うように新しいこと、物珍しい暮らし方に手を出す性癖があったように思われます。
母を失ってからロシアには住み続けようと思わず、飛び出して船に乗り、やっとたどり着いたアメリカに数年暮らした後、普通だったらやっと定着するような時期に中国に移住、ここも住むところにあらずと思うと、何もかも捨ててアメリカに戻りながら、再び飛び出して、日本にも定着できずに、結局日本以降の足取りはつかめていません。仕事も、あれやこれや手を着けて、ケチが付くとスッパリと辞めてしまう。映画人として名前をどこにも残せなかった理由はこの辺にあるのかも知れません。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT