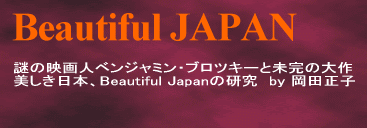
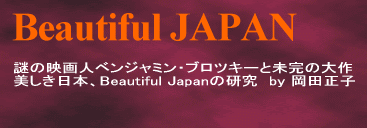
1.大正時代に撮られた日本紹介映画『BEAUTIFUL JAPAN』
1993年、財団法人下中記念財団EC日本アーカイブズ(ECJA)は、昭和の初期、1933年から34年にかけて北海道沙流郡二風谷でスコットランド人の医師ニール・G・マンローによって撮影されたアイヌの悪魔払いの儀式「ウエポタラ」1)と新築祝いの儀式「チセノミ」2)の復刻版を製作しました。長い間劣悪な状態で放置されていた映像の復刻版製作に当たって、財団では二風谷出身の現代のアイヌ民族代表者の一人、萱野茂氏に解説をお願いしたところ、萱野氏のお祖母様に当たられる方がマンロー医師のインフォマントであり、同映像には踊り手として出演されていたことや、萱野氏ご自身もこの撮影のことを幼少時代の記憶として覚えておられ、そんなこともあって快く解説を引き受けて下さいました。長年の念願であった復刻版が完成したこともさることながら、マンロー医師が意義を感じられたこの民族の固有文化遺産を萱野氏を通じてアイヌの次々世代の方々に伝えられたことが何とも嬉しく、また萱野氏を通して60年も以前の二風谷の様子、マンロー医師の人となりについて伺えたことで、なお一層充実した印象深い仕事になりました。

映画「美しき日本」のメインタイトル 映画「美しき日本」から白老アイヌの長老たち
そんな折り、復刻版製作の指揮に当たったECJAの所長である私の主人岡田一男(東京シネマ新社代表)から「大正時代にもアイヌの生活を映像に収めた人がいて、その作品が実際に見られる形になっているんだよ。これがそうだ。」といって手渡されたのが『BEAUTIFUL
JAPAN(美しき日本)』です。140分の作品の中に、ほんの数分ですが北海道白老で撮られた「熊送り」の映像が映っていました。映像は、カメラがゆっくりと左方向にパンしてアイヌの村の概観を紹介し、一つの住居が画面の中央に示されます。それから若い男たちによって住居の傍らにある木製の囲いの上部からコグマが引っ張り上げられ、そのコグマの首に紐が掛けられ、村の長老エカシ等が並び座る前に連れ出されます。エカシたちは儀式の酒を飲み交わし、女性たちの踊りに続いて男女の踊りが披露されます。シーンが変わるごとに英語で書かれたタイトルが入り、アイヌ民族の来歴、儀式の意味等の説明が簡単に示されます。森で出会った熊を捕らえて神のもとに送る西シベリア、ハントィ民族の「熊送り」などと違って(もっともハントィの人々は“迎えて”いるのだと主張するでしょう)、アイヌの風習では各村でコグマを大事に育てあげ、そのクマを神のもとに送ることが知られていますが、映像に映っているコグマがやけに小さく、実際に神に送る場面がないこと、本来屋内で行われる儀式が屋外で執り行われていること、並び座ったエカシたちがカメラを少々意識し、互いに目配せをしながら酒を飲み交わすこと等から、これが映画撮影のために行われた模擬儀式であることが判ります。踊りなどを含む各シーンが思いのほか丁寧に撮られているものの、アイヌの文化を知るためには少々短すぎるカットです。
私が『BEAUTIFUL JAPAN』を見たのは以上のような経緯があり、当初アイヌの映像を見る目的でしたが、その短いシーンを探すために作品全体をざっと見てみると、北は北海道から南は九州まで、日本の全国各地で撮影された興味深い作品であることが判りました。都会で撮られたシーンの中には、戦後の荒廃した東京の街で見かけたような風景、つまりコンクリートやアスファルトに囲まれる以前の、年輩の日本人の記憶の中にまだ残像として刻まれている古い東京と似た風景も映っています。また、農村風景はほんの少し前の、機械化が進む前どこにでもあった日本の農村です。が、全体的には、特に女性や子どもたちの衣服、髪型から、あるいは陸軍兵隊の行進する姿が映っているところ等から、やはり古い時代の映像ということを実感しました。
『BEAUTIFUL JAPAN』というタイトルは、この映画が日本を外国に紹介する目的で作られた作品であることを示しています。しかし一通り見た処、作品として筋道の通った編集がなされないままフィルムがつながれているという印象は拭えません。この点については、この映像を私の仕事場で見られるようになったさらに詳しい経緯を聞いて何となく大筋では納得することができました。
1991年(平成3年)2月に北海道網走市に開館した北海道立北方民族博物館の要請を受け、岡田一男は世界に散在する北方少数民族とその文化を示す映像資料を収集するお手伝いをしたのですが、その過程でスミソニアン協会国立自然史博物館人類学フィルムアーカイブズ(Human
Studies Film Archives, =HSFA)の所蔵する『BEAUTIFUL
JAPAN』という作品に、日本の最北端に住む少数民族アイヌに関する古い映像がふくまれていることを知りました。スミソニアンからベーターカム・ビデオコピーの形で『BEAUTIFUL
JAPAN』の提供を受けた際、同協会担当者デイジー・ラッセル・ンジョクさんから「これは、製作者ブロツキー自身によって、当時の駐日米国大使ローランド・モリスに贈呈された35ミリフィルムのコピーないしその一部です。第二次大戦後、自宅に死蔵されていた9巻のフィルムは、大使の遺族ウィリアム・マクホルド夫人により私どもスミソニアンHSFAに寄贈されました。寄贈されたフィルムの9つの缶には1から9までの番号が付られていたので、HSFAでビデオ転換する際、第1巻と2巻を各1本の30分ビデオカセットにコピーするという方法で5本のベータカム・ビデオテープを作成したのです。」という説明を受けました。つまり、マクホルド夫人が自宅で見つけられたのが9つのフィルム缶であり、それぞれに『BEAUTIFUL
JAPAN』と記されており、通し番号が就いていたかも知れないけれど、通し番号を誰が、いつ付けたのか不明であり、つまりそれはもしかするとブロツキーが編集したもののほんの一部かも知れなく、また何も番号順に140分の作品として見なければならない完成版とは限らないわけだったのです。現在、ブロツキーがモリス大使にどんなきっかけでフィルムを渡したのか、その際、実際にはどの位の分量のフィルムを渡したのか、記録は見つかっておらず、残念ながら判っていません。
『BEAUTIFUL JAPAN』の中のアイヌの映像が北海道の白老で撮られたことは、そのシーンの冒頭に挿入された英語のタイトルから判ったのですが、同様に各シーンが変わるごとに、全てとはいえないのですが、どこで撮られた何の映像であるかが分かるように英語の説明タイトルが付されているため、サイレント映像ですが情報量は豊富です。


日本帝国国有鉄道の格別の後援 ブロツキー自身が登場する
第2缶の冒頭(CN:02:00:39)には、星条旗・日章旗に囲まれこの作品のメインタイトルである『BEAUTIFUL
JAPAN』という文字が記され、画面右下に描かれた扇子の中には「T.F.K.」とあります。つづいて英語で「製作:ベンジャミン・ブロツキー活動写真会社、特別後援:大日本帝国政府鉄道院」とあります。また、当のベンジャミン・ブロツキーの姿が一瞬ではありますが映し出されます(CN:02:08:29)。それから手に指示棒を持った男性が、画面一杯に貼り出された日本地図上を列車が通った道筋を示すように棒を動かし(CN02:08:29)、その後、日米の国旗を付けた列車が画面に登場することから(CM:01:05:25, 02:08:29, 05:24:09
)、この映像が北海道から九州まで日本中を日本政府鉄道院が提供した列車で日本を縦断移動しながら撮影された日本紹介映像であることが分かる趣向になっています。


日本地図で旅程を示す 撮影隊に貸与された特別列車
日本地図で示される道筋が、撮影旅行をした結果の道程を示したものか、あるいは旅行の前に立てた単なる予定の道程としてしめされたもの、またあるいは映像が紹介される順序を示したものか、確認は取れていません。しかし、わざわざ日本地図上に道程まで示しているにも関わらず、実際のフィルムのつなぎ方は、道順に並べられていないこと、さりとて一定の内容にそってつながれたとは到底思えないことが不思議でした。そこで、地図に示された道程のどことどこで撮影が行われたのか知るために、まず『BEAUTIFUL
JAPAN』のショットリストを作成する一方、各カット変わりに挿入された英語のタイトルやコメントを日本語に置き換える作業に着手しました。
ところで、日本と日本の文化を、外国、特に欧米の国々に認知して欲しいとの日本国としての願望は、日本が鎖国を解き明治維新を迎えた当初よりあったようで、どのような方法で自国を紹介をするかという点について、日本政府としては『BEAUTIFUL
JAPAN』以前にも様々な試みを行ったことが知られています。1893年3月に渋澤栄一、益田孝等により創立された任意団体ウェルカム・ソサイエティーの事業内容を継承する形で1912年(明治45年)3月に設立されたジャパン・ツーリスト・ビューロー(JTB、社団法人日本旅行協会、現在の日本交通公社の前々身)が後年発行した同ビューロー40年史、50年史、70年史等に初期の外客誘致試案が立てられた事情、経緯が詳しく述べられています。
上記の目的以外にも、明治、大正政府が外貨獲得の必要にも迫られており、外客誘致が有効であると計算を立てた上で官民が協力しあって様々な計画を実行に移したことなども記録しています。JTB設立を知らせる新聞記事(報知新聞)に「本協会発起の趣旨は我国が今日海外に負いたる大債務の元利金は年々八千万円を超え、これが償却や容易にあらず。然るに我国は山水の風致に於いて世界に冠絶し、外人の普ねく憧憬する所なるを以てこれを利用して観光外客を誘引勧奨して、外資を吸収するは最も捷径且つ有効の方策なりと云ふに在りと我らは双手を挙げて斯挙を賛成し其の成功を祈らんとす。」とあります。JTBが実際に行った単行本、雑誌、パンフレット、サーキューラー等の印刷物の配布はもちろん、ポスター、絵葉書、写真の印刷、幻灯写真の製作、講演会、展覧会の開催などを通して、風光明媚で固有文化の豊かな国であることを積極的に紹介していたようです。
1937年(昭和12年)に発行されたJTBの『回顧録』3)には、日本政府の努力・試みに触れて、外国の新聞・雑誌への紀行文の投稿、印刷物の配布などを試みた後、最終的に「活動写真で日本を撮影し、それを外国で上映する」ことが最も有効な手段であろうという主張が出てきたと記録した上で、「撮影は外国映画人に委託する」という意見に傾いたとあり、その理由として経済的な理由を挙げています。実際には、技術的な問題等も大きな要因であろうと思います。大正に入る頃には、日清戦争(1894−95年)、日露戦争(1904−05年)に形の上で先勝した勢いをかりて、自国が西欧諸国に正統に認知され、評価されなければならないという願望は切実さを増し、特に第1次世界大戦直前、アメリカに移住した日本人に対する差別問題が表面化(日本人の白人住宅地からの締出し、排日感情むき出しの映画の製作上映等々)し、その問題が外交問題にまで発展するにおよんで、これは日本人とその文化に対する無知から来ることであろうということになり、日本紹介映画製作を政府を挙げて支援するという案が具体的な外国人映画製作者との交渉にと移行していったようです。
JTBは日本国政府鉄道院から基本資金が供出され、鉄道、汽船、ホテル、外国人に関係を持つ劇場、商店等の寄附によりつくられた協会です。従って、初代の会長は鉄道院副総裁が兼務し、理事には鉄道院を始めとして台湾鉄道、朝鮮鉄道、満鉄、大阪市電気鉄道、日本郵船、大阪商船、東洋汽船、帝国ホテル、三越等の重役が就任しています。
日本の映像記録を作るため最初に外国から来日したのはJTBの設立より早く1897年(明治30年)で、フランス、パリで開催された万国博覧会においてリュミエール兄弟によりシネマトグラフと名付けられた映画が世界で始めて公開されてわずか2年の後のことです。映画というメディアの誕生と直接関わり、以来、外国の情報などがなかなか届きにくかったこの時代に、世界の各地で積極的に映像による記録に取りかかることにしたリュミエール兄弟が興したリュミエール社は、撮影技師コンスタン・ジレルとガブリエル・ヴェールを日本にも派遣したのです。勿論プロジェクター等の機材一式を携えて撮影技師は来日したのですが、このリュミエール社で開発したプロジェクターがカメラと現像機の機能を兼ね供えていたことと、ヨーロッパにおける観客を飽きさせない上映をする興行的な見地から、新たに映像を撮り足す必要があったため、映写技師ジレルとヴェールが撮影技師も兼ねて日本各地の映像を撮り貯めました。この時に撮影された映像は、通称『明治の日本』4)という題名が付けられ現存します。
この映像はNHKのTV番組でも紹介されたこともありますし、また映画発明100年を迎えた1995年には記念行事の一環として東京渋谷区にある松濤美術館等において上映され、また同年、リュミエール社の日本での撮影について詳しく書かれた本『映画伝来 シネマトグラフと〈明治の日本〉』5)が岩波書店から出版されました。(『映画伝来』の著者のお一人古賀太氏は、同書で『明治の日本』という題名に異議を唱え、むしろ『リュミエール映画日本編』と呼ぶべきではないかと書かれています。)因に、この通称『明治の日本』と呼ばれる映像にもアイヌの踊りのシーンが出てきますが、これはアイヌ民族の映像記録としては最も古いものであるといわれています。

ジレルが1897年に記録したアイヌの踊り ブロツキーが1917年に記録したアイヌの踊り
リュミエール社の撮影以降も、日本に関する映像は欧米の観衆に受け入れられ、評判を呼んだため、外国映画人による撮影申し込みが引き続き、その中の幾つかは実行に移されたようです。今回の調査で見つけた新聞記事の中には、企画が実行に移されたかどうかは不明ながら「セオドア・ルーズベルト米国前大統領の従弟が中心になって取材を申し込んできている」6)というものもありました。前述の『回顧録』によると、幾つか実行に移された外国人による撮影の中で最も大がかりだったのは、リュミエール社撮影から遅れること20余年、1917年(大正6年)に来日した米国籍のベンジャミン・ブロツキーの撮影旅行だったということです。
英国のオックスフォード大学の社会人類学教室がインターネット上で公開しているハッドン7)というデータベースがあります。これは初期の映画で、人類学上有益と思われるものの所在情報を蓄積しているデータベースです。ハッドンという名前は、1895年にオーストラリア最北端のトレース海峡で英国最初の民族誌映像を記録した英国人類学の先駆者アルフレッド・コート・ハッドンに由来します。HSFAはもちろんこのデータベースに『BEAUTIFUL
JAPAN』を登録していますが、このデータベースを眺めてみると、映画の黎明期、日本という国が外国から並々ならぬ関心を寄せられたエキゾチックな国であったことが分かります。そのような諸外国の関心の高さを日本政府が利用しようと考えても不思議ではなかったのです。
前述のJTB『回顧録』にある日本紹介映画製作に関する部分には以下のように記されています。
映画は費用の関係からビューロー自身でつくることは不可能であったので、
海外の映画会社に撮影を勧誘し、来朝の場合充分斡旋するという状態であった。
この意味で最初斡旋した撮影班は巴里活動写真会社の特派員モロー氏一行で明
治45年5月来朝、日光、松島、箱根等の風景並芸者の踊りなどを撮影して帰
った。最も大掛かりだったのは大正6年(1917年)10月来朝した米国東
洋フィルム会社の撮影班で、一行は数名の男女俳優を同伴し本土、北海道、九
州の各地に亘り撮影し、須磨や明石では海岸を背景として物語風の作品をつく
り、大村湾では真珠採取の実況を、別府では日名子旅館で「寝室」と「寝室に
入る迄の過程」を撮影した。一行の撮影に就いては終始掛員を附添わしめ鉄道
院や地方当局と連絡をとり充分便宜を計った。
巴里活動写真会社のモロー氏の名前をわざわざ記しながら、ブロツキーの氏名はここには記されていません。しかし、ここで述べられている大正時代の撮影隊がブロツキー一行のものであることは、残っている映像の内容がこの文章中の「撮影した」と記述されている各シーンに該当すること、また東洋フィルム会社という社名が、映像中ではベンジャミン・ブロツキー活動写真会社となっているものの、他の資料によるとブロツキーが横浜山下町に設立した会社の名前であることなどから確認がとれました。来日期日については、後で詳しく記しますが、少なくもブロツキー自身の来日はここに記述されている年号より遙かに以前ではありますが、『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影は大正6年に行われたことがここに判明したわけです。この映画撮影には、日本政府は鉄道院から列車一編成(蒸気機関車、客車三両、乗用車一台)を提供し、JTBから終始世話係を添乗させました。
1973年(昭和47年)にフィルム・ライブラリー協議会が発行した「日本映画史素稿8 資料 帰山教正とトーマス栗原の業績」には、当時教育映画配給社社長をされていた金指英一氏の執筆になる「大活前史 東洋汽船と大正活映」が載っています。その中で金指は「この頃(第一次世界大戦開戦中)、外務省の石井菊次郎、鉄道院の木下淑夫次官、ツーリスト・ビューローの生野団六氏等が、東洋汽船、日本郵船、大阪商船、満鉄、日本の一流ホテル業者と会合し日本紹介映画を作ることを検討した」と記しています。この会合の開催年月日が不明なのは残念ですが、具体的に官民挙げて日本紹介映画製作に乗りだしたことを示す記事です。国側としては先に記した事情から外客誘致を計ることが国策として有効であるとしたものですが、実際に寄附を出した民間企業にとっては、倫理・道義上この計画に賛成したばかりではなく、各々企業としての計算も働いていたことは当然であり、その一例として東洋汽船浅野総一郎の場合を例に取って後述します(7.浅野総一郎、良三父子とブロツキーの項目参照)。残念ながら金指氏の文章は、官民合同の外客誘致のための映画製作について述べながら、その計画の話がその後どうなったか尻切れトンボで終わっています。また氏の文章では、東洋汽船の浅野良三が大正活動写真株式会社設立以前に日本紹介映画制作を支援した点について簡単に触れていますが、この文章では「第一次大戦後である」としている点が事実と異なるように思われます。
日本国はどういう理由で複数の申し出の中からブロツキーへの支援を決めたのでしょうか? そもそもベンジャミン・ブロツキーとは一体何者なのでしょう? そして、ブロツキーと日本側が長時間を掛けて交渉し、力を注いで製作した筈の完成作品がこのスミソニアン協会HSFAで見つかった映像なのでしょうか? この撮影についての公的記録として鉄道関係の文献を探したのですが、唯一見つかったのがJTBの『回顧録』で、鉄道院を引き継いだ国鉄(現在はJRの民間各社)の記録には一切残っていないようです。なぜ公的に殆ど記録されなかったのでしょうか? 映像『BEAUTIFUL
JAPAN』は期待されたように外客誘致に大いに役立ったのでしょうか? こういった点について『回顧録』には触れられておらず、疑問は調査を進める内にかえって多くなってゆくばかりでした。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT