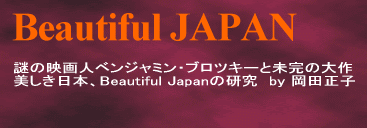
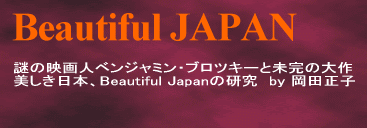
8.ハリウッド俳優トーマス栗原を東洋フィルム会社に迎える
トーマス栗原監督し谷崎潤一郎が文芸顧問を務めた大正活映の第1作「アマチュア倶楽部」の記念写真
ブロツキーがアジアでの活動を始めた頃、アメリカではエキゾチックなアジア、日本や日本人がストーリーに絡まる映画が多く作られていました。後に『クワイ河の戦い』に出演した早川雪洲などがハリウッドでデビューしたのがこの時代です。早川は1914年『タイフーン』という映画でトーマス・ハーパー・インスと共演しています。このインスについては先にも述べましたが、まず興行劇の俳優の子として生まれ、俳優としてデビューした映画界でその後、製作者・監督として一斉を風靡する働きをしています。
1910年代、インスの下には数多くの映画製作者、俳優が集まっていました。金指氏はブロツキーもその中の一人だと述べていますが、先に述べたように、それはブロツキーの年表を作って見ると無理があるような気がします。ブロツキーはインスのところに「いた」というよりむしろ「行ったことがある」といった方が正しいのではないかと推測します。ブロツキーは来日前に中国を本拠地とし、中国各地で撮影したドキュメンタリーを『A
TRIP THROUGH CHINA』という作品にまとめ米国で上映するために、サンフランシスコを拠点にして全米各地に働きかけていました。ブロツキーの作戦は成功し『A
TRIP THROUGH CHINA』はアメリカで大いに受け、当時の新聞にその評判が記録されました。
同じように1917年、日本で撮ったフィルムの売りこみに渡米しますが、この時は全く問題にされなかったのか、その渡米に間する記事はアメリカでは全く見つかっていません。この旅行の際にインスの下に日本人の俳優も数名集まっていたところから、ブロツキーがインスを訪ねたのではないか、それがあったからこそ翌年、日本人俳優およびアメリカ人スタッフを日本に招くことができたのではないかと推測しています。その際に来日した一団の中にインスの下で俳優として働き、既に名の知られていたトーマス栗原喜三郎がいたのです。栗原はインスの下にいた日本人俳優の中では最も古株であり、才能に恵まれていると自他共に認めた俳優でした。
1918年(大正7年)、ブロツキーは『BEAUTIFUL
JAPAN』以後のことを考える時期に来ていました。前年から日本紹介映画のためには映像はかなり撮り貯めていましたから、次なる仕事は劇映画にしようと計画を練っていました。インスの下を訪ねたブロツキーは栗原に出会い、自分が撮っている日本のドキュメンタリーを完成させ、その後は日本で劇映画を撮り、それをアメリカ市場に売り込む計画を持ちかけました。その話に乗ったのは栗原だけではありません。他に木野五郎、小林某の日本人俳優がこのブロツキーの誘いに乗り、その外にアメリカの映画人が加わり、合計15名を引きつれてブロツキーが横浜港に戻ったのは1918年(大正7年)4月1日です。
新聞記事から日にちは確かめられたのですが、ブロツキーの説得がこのように大勢の外国人を含むアメリカの映画人に受け入れられるためには資金の目処が既にたっており、東洋フィルム会社は企業として長期展望もあったものと思われます。つまりブロツキーと浅野との提携はすでにあったという証明になります。横浜港で行われた撮影関係者インタビュー記事が横浜貿易新聞同年同月3日付けに掲載されています。(なお、この記事にある東洋フィルム会社の住所は53番地というのは間違えで実際は31番地です.)
『桑港の東洋フィルム会社にて、先にブロドスキー氏一行の男女俳優を
日本に派して、各種の映像を撮影し帰りたるが、その際、当市(横浜)
山下町53番地に事務所を設け、オリエンタル・ホテル裏手に建設中なる
撮影場もほどなく落成したるをもって、今回はブロドスキー氏はじめ、
新たにキーストン、ユニヴァーサル等の活動俳優一行15名を派すること
になり、1日午後、春洋丸にて来着せり。しかして、一行中に桐原、木
野、小林の三日本人俳優ありて、交々語る。「今度は先ず喜劇を撮るん
ですが、背景は日本でも筋はやはり米国向きの物語で、おとぎ話のよう
なものも好かろうと思います。一行の中のベーリーと云うのは舞台監督
で、チャップマンと云うのが道具方ですが、持ってきた自動車二台の中、
一台は壊すために持ってきたのです。女優ですか? 勿論来ましたとも。
クッチ嬢なんてのは、なかなかの尤物ですよ。ご紹介しましょうか?」』
ここで桐原と呼ばれているアメリカ帰りの日本人俳優はトーマス栗原喜三郎です。栗原自身がこの日付で帰国し、それから日本に7ヶ月間滞在したと証言しています。木野は木野五郎で、「タイフーン」で早川雪洲と共演以来「早川一座主要俳優」といわれ、ユニヴァーサル映画社製作の「薄命の女」に出演した俳優だろうと思われます。東洋フィルム会社は「サンフランシスコの」と形容されています。他にも「アメリカの」「米国の」東洋フィルム会社という表現が様々な文書に見られます。このことが日本の映画史からブロツキーとその活動を外すことになった一つの原因かも知れません。さりとて事務所の本部は横浜にあるわけですからアメリカの映画史に残るわけもないのです。
既に述べたように、その後撮影を無事終了した『BEAUTIFUL
JAPAN』の編集からブロツキーは外され、替わってトーマス栗原が同じ素材を使って『美しき日本』を完成させ、1920年12月に大正活映製作第2番目の映画作品として、東京市にあった浅草千代田館で発表しました。これより以前、東洋フィルム会社の時代に『BEAUTIFUL
JAPAN』とは別に、栗原監督作品の劇映画『成金』と『東洋の夢』を製作し、1919年春ブロツキーは新作を携行して、今度はトーマス栗原、尾崎庄太郎を伴い、再びアメリカに売りこみに行きました。この二作品は凡作だったのか評判を呼ぶことはありませんでした。
『成金』に関しては、大正活映の作品目録を見ると、トーマス栗原監督作品として1921年9月2日(大正10年)に初演されたという記録があり、この2作品が同一のものか未確認です。東洋フィルム会社版『成金』製作に関与した人物として、ベンジャミン・ブロツキー(製作)、トーマス栗原喜三郎(監督)、アームストロング(撮影)、稲見興美(撮影)、ベーリー(舞台監督)、尾崎庄太郎(舞台)、チャップマン(道具方)、クッチ嬢(女優)、中島洋好(主役男優)、木野五郎、小林某(男優)等の名前が記録に載っています。
その後、ブロツキーに関して分かっていることは急激に減ります。1920年(大正9年)4月、ブロツキーは東洋フィルム会社の建物、機材を含む全てを浅野良三に譲渡して同社を去ります。それから、年月日は不明ですがブロツキーは自分なりに編集を仕掛けていた『BEAUTIFUL
JAPAN』の素材の一部かもしくは全てをローランド・モリス大使に託しました。大使が日本を離れたのは同年の5月です。
そしてこの年、良三は東洋フィルム会社の社屋をそのままに「大正活映」(当初の正式社名は大正活動写真会社)を興しました。ところが、旧居留地の国内外の企業名が全て記載される筈のこの年のディレクトリー本文には「東洋フィルム会社」の名も「大正活映」の名も見当たらず、索引にのみ「東洋フィルム・フィーチャー」という社名が元「東洋フィルム会社」の住所、つまり山下町31番地に所在していると記されています。索引に載っているだけなので、この会社の代表者名、支配人名などは割愛されています。この状態は1921年も続きます。1922年のディレクトリーからはブロツキーの名前はおろか「東洋フィルム・フィーチャー」の会社名も削除されています。
1923年に初めて「大正活映ラボラトリー」の名が同社の英文名として同ディレクトリーの本文に登場しますが、この年は大正12年にあたり、前年の9月には「大正活映」が松竹キネマと業務提携し、大正活映としての映画製作活動を終えたことを考えると、ディレクトリー記載事項は事実と相反するように思われます。浅野良三の個人年譜には彼が「大正活映」の社長を1925年(大正14年)まで勤めたとしているところから(人事興信録第7版、大正14年出版)、実際に同社の営業報告を調べてみた処、大正活映は松竹キネマに映像上映権を3年契約で譲渡した上で休眠状態に入りました。
この3年間、大正活映は上映権報奨金を松竹キネマより受け取ることで経済の建て直しを計り、3年後の契約満了時には映画製作を再開しようという当初の計画でした。ですから、映画製作は1922年(大正11年)に休眠したものの、会社自体は1926年(大正15年)まで存在していました。しかし、1923年(大正12年)9月1日に見舞われた関東大震災により松竹の被害が予想外に大きく、報奨金の支払いさえ滞り計画は実行されなかったのです。
1926年(大正15年)9月、トーマス栗原は42歳の若さで亡くなり、雑誌『映画時代』のその年の11月、近藤伊与吉氏が追悼文を書かれています。それによるとトーマス栗原は「映画製作は監督本位」で行われるべきであると主張する「徹底的活動写真的写実主義」であったとあります。これは将にインスのモットーだったといわれています。当時の写実主義とはどのようなものか知るためにもトーマス栗原監督の『美しき日本』を見てみたいと思いますが、残念ながらこの作品は大正活映製作作品としては第2番目の作品としてリストに載り、1920年12月には東京、浅草千代田館で公表されながら、原版、プリントなどは現在見つかっておらず、鑑賞したという関係者の証言もなく、作品内容についての詳細、長さなどの形態等、全く分かっていません。ブロツキーの『BEAUTIFUL
JAPAN』と比較してみたらどんなに面白いかと思うのですが。
大正活映でドキュメンタリーと劇映画を併せて29本の作品を監督したトーマス栗原の作品は、現在残念ながら残っていることが確認できる作品は大正9年製作の『後藤三次』1本です。彼の業績としては監督としての活躍の外に俳優の養成が挙げられます。全くの素人に演技を教えるその作業はかなりストレスの多い仕事であったようです。既にアメリカにいる頃胸の疾患を覚えていた栗原には荷が重すぎるほどでしたが、アメリカでは俳優として身を立てた栗原ですから、彼にはもっとも得意分野でもあったでしょう。
トーマス栗原やヘンリー小谷等のようにアメリカの映画界に育ちつつあった日本人映画人は思いのほか数が多いようで、その中でもこの二人はアメリカでの安定した暮らしを投げ打って故郷日本の映画の発展のために帰国したようにいわれています。しかし、文化的・経済的環境はともかく、アメリカ側が製作する奇妙な東洋趣味作品への関わりには限界が見え、自分たちの力は日本の映画界において発揮した方がより有効であろうと信じて彼等は帰国したのではないでしょうか。大正活映で映画人としてその第一歩を踏み出した後の劇映画監督内田吐夢氏は著書『映画監督50年』の中で「谷崎(潤一郎)先生は江戸っ子で、気安く、包容力があり、牧師型の厳格な栗原先生にはよりつき難かったので、私たちは先生になつき、むしろ甘えすぎるほど甘えていた」と書いています。
大正活映を知る誰もが、トーマス栗原の熱心な、そして真摯な仕事ぶりには目を見張り、多くを学ぼうと新しい劇映画の波を起こす栗原の目覚ましい働きに触発されたようです。その栗原について知るほどにブロツキーが、彼と一つの作品の製作に取りかかっていたことに無理があるように思われ、その仕事が結局決裂という形で終わったことは何となく頷ける気がします。
トーマス栗原については日本映画史に足跡を残した人物ということで多くの文章が存在するところから、ブロツキーと浅野のつながりが確認できたりといった副産物もありました。彼の軌跡を現段階で分かっていることですが記してみましょう。
1874年(明治7年) 小田原に生まれる。
? 年 渡米。
1912年(大正元年)春 アメリカの俳優養成学校に入学。
ケールム会社入社。その後、シーリング社に移る。
1913年(大正2年)11月 トーマス・H・インスの配下に俳優として参画。以来4年間、インスの指導を受けながら研鑽。
1917年(大正6年) 白人と共同して日米親善の啓発運動を理想とする会社を設ける計画を立てたが時至らず中止となる。
ロサンゼルス北サンペドロ街に日本人活動写真俳優組合を組織。栗原は評議員となる。
1918年(大正7年)3月 エッサネー、ラスキー、フォックス、ハート、トライアングル社等の映画に出演。
4月 トーマス栗原、来日。7ヶ月滞在。浅野と知り合い、東洋フィルム会社に参画。
11月25日 東洋フィルム会社製作の『成金』『東洋の夢』を引っさげてサイベリア丸に乗り横浜港出航し、アメリカに向かう。
ブロツキーも同行。5ヶ月滞米。紐育市場の研究、映画製作技術の研鑽。
1919年(大正8年)12月 渡米。
1920年(大正9年)2月 帰国。
5月 大正活動写真会社、創立。
7月 大正活動写真会社、大正活映と改称。
11月19日 『アマチュア倶楽部』公開。大正活映第1作。
12月23日 『美しき日本』公開
『葛飾砂子』、『後藤三次』、『明治神宮鎮座祭』公開。
1921年(大正10年) 『元旦の撮影』、『泥の災難』、『五万円』、『神の摂理』、
『雛祭の夜』、『夢の旅路』、『米国曲芸飛行』、『出帆
前怪指紋』、『喜撰法師』、『加州大学野球団来朝戦実況』、
『岩見重太郎武勇伝 弱者の夢』、『保津川下り』、『狂
へる悪魔』(栗原、監督、出演)、『成金』『蛇性の婬』(栗
原監督。当麻酒人の名で出演)、『大日本帝国』、『煙草
屋の娘』、『薄命の女』、『東宮殿下台覧ボートレース』、
『紅草紙』、『雪解けの夜』公開。
1922年(大正11年) 『軍鑑陸奥』、『英国皇太子殿下台覧の外相邸の娘道成 寺』、『大隈候の国民葬』公開。
1923年(大正12年) 栗原、ヘンリー小谷映画『舌切雀』に出演。続いて同
映画で『続アマチュア倶楽部』監督、出演。
1924年(大正13年)11月22日 栗原、小笠原プロで『久遠の響』を監督。
栗原『苔のむすまで(主義の戦ひ)』を監督。
1925年(大正14年)10月 トーマス栗原、内田吐夢・近藤経一の特作映画社に参加。『極楽鳥の女王』に出演。
1926年(大正15年)9月8日 死去。享年42歳。自宅:横浜本牧町
栗原のアメリカ時代に煩った肋膜炎は、過激な労働の中で徐々に悪い方向に向かい、遂に昭和を向かえることなく42歳で亡くなりました。大正活映で文芸顧問として共に働いた谷崎潤一郎は、栗原の死を悼む記事を雑誌『活動画報』に載せ、才能もあり努力家であった栗原が「薄給に甘んじ、撮影所を一人で背負って立つ程の多大な仕事を負わせられながら、欣々として勤めてい」たのに「会社の首脳部の人々が栗原君の爪の垢ほども誠意がなく、いかに無能であったかを語るに足りる」と苦々しく語っています。
最近、大正活映に関係する新聞記事を見付けました。
横浜貿易新報 1920年(大正9年)5月11日付けの
不景気を控えて活動館が2,3軒新たに目論まる
当然の反動として不景気は来た。世間景気のバロメートルたる花柳界
にも興行界にも、先月以来弛みが見え始めた。東京ではさすがの松竹
キネマ合名の株までも大打撃を受けていると伝えられる際、当市には
新たに二三の活動設館は目論まれている。其の一は花咲町8丁目85
番地に創立事務所を設けた帝国活映興行株式会社、其の二は山下町に
あるサンライス、フィルム会社、其の三は程ケ谷に敷地を物色して未
建設の永楽館。之等を重なるものとして角力常設館を手放した加藤弥
惣次氏は南吉田町辺に、横浜劇場の山本藤次郎氏は北方辺に、何れも
常設館建設の噂がある。
右の中、帝国活映は一百万円の資本発起者は横浜駅前の市街自動車会
社の重役連と湯澤横須賀電気館主、同地渡邊朝日館主、矢田三崎日の
出館主、鈴木神奈川金鵄館主等で顧問には石井日活支配人を挙げてい
る。目的は県下における既設常設館を買収し、且つ諸所に新館を建設
して活動写真興行をなす外、フィルムの賃貸等をなすものらしい。4
分の1払込に10万円の借入れ金即ち35万円を以って先ず差当たり
2,3館の買収費と新設館費とに当てる予算になっているが、果たし
て巧く行くかどうか。サンライス、フィルムの方は大正活動写真会社
といふ東洋汽船の栗原氏及び外人等の運営で、常設館を得るまで当分
東京、大阪、京都、横浜等の劇場を借り受けて年数回挙行する筈で、
其の第一回を近く有楽座でゴールドウィン社物を封切りする。又一面
には谷崎潤一郎氏あたりの純文芸物を脚色撮影するさうである。この
文芸物には従来の鳴り物や説明などを避けて、音楽一方で見せる高尚
な映画にするとのこと。この計画も役者を得るのは困難でもあろうし、
且つ営利事業としては一寸成算は逸れ勝らしい。程ケ谷にできるのは
元神奈川演芸館にいた永久保鉄五郎氏と保土ヶ谷有志の計画で早くも
建設認可を出願したと云はれて居る。写真は日活の供給を仰ぐものら
しい。加藤氏と山本氏の物は未だ形を成して居らぬ。兎に角不景気来
の場合とて、同業者から興味を以って眺められている。
ここでいう、サンライズ・フィルムはブロツキーがサンフランシスコで属していた映画興行会社で、栗原氏とはトーマス栗原です。トーマス栗原は東洋汽船とは独立して存在していた大正活映の監督として契約していた筈のところ、東洋汽船の社員であるように書かれていますが、この二つの会社が両方とも横浜山下町にある浅野系の会社であったため、横浜で浅野といえば東洋汽船という認識で混同してしまったのかもしれません。大正活映は果たして、横浜貿易新報の記者が危惧を感じていた通り、短期間の内に運営破綻してしまったことは前述の通りです。しかし、娯楽の種類の少なかった当時、映画館に通う人の数は多く、また洋画の興行館の少なかったことも手伝って、映画館経営は全般的に成功したようです。なお、東洋フィルム会社が大正活動写真会社に改組されたことにより、現在、大正活映の撮影所跡として記念碑が立っている元町公園の一角は、東洋フィルム会社の撮影所跡でもあることもここに明記しておきます。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT