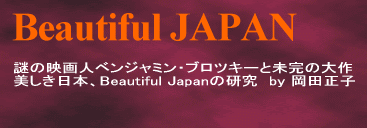
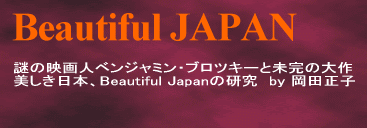
7.浅野総一郎、良三父子とブロツキー

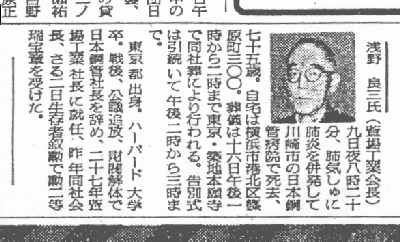
浅野造船所の進水式に望んだ浅野総一郎(右)
総一郎の子息、良三の死亡記事
ブロツキーはドキュメンタリーを製作するにあたって、中国においても日本においても権力者と渡り合った上で許可、支持、支援されて撮影をさせて貰っています。記録によると中国では紫禁城に入ることを許され、映画の撮影をした最初の白人であるということですし、西太后の葬儀の撮影にも成功しています。それと比較すると、日本で撮られたものの中には皇居の中にカメラを持ち込んだ形跡はありません。内堀の外側から撮られた映像が残っているばかりです。ブロツキーの後援先がそれぞれの国において保持していた権力の大きさの違いなのでしょうか。
もっとも、ブロツキーの撮影した映像が全部残っているわけではないのでこの点、何ともいえませんが。中国の映像には袁世凱の家族がくつろぐ姿が映っているところから、『中国時報』の張記者は、時の権力者袁世凱の子息がブロツキーと船乗り時代の知り合いであって、中国におけるブロツキーの協力者は袁世凱であったと推測しています。
それに対して、日本における後援者は浅野コンツェルンの総師者浅野総一郎とその子息浅野良三(次男)と断言できるかと思います。現在の処、浅野以外の人物がブロツキーの周辺にいたという記録はなく、大正10年の雑誌記事で東洋汽船の浅野総一郎が資金を提供し、東洋フィルム会社を設立したと明言しているものを見付けました。そして同社の支配人はベンジャミン・ブロツキーであることはジャパン・ディレクトリーに記されて確認されています。
一つこの推論に反論する証言があるとすれば、後述する「運動会」のシーンの撮影に際してブロツキーは学校側に「アメリカ合衆国官憲の命により」撮影するといっている点です。これは実際ブロツキーがそのように表現したのか、学校が文書記録にする際にそのように記載する必要を感じたのか、どちらとも今となっては証明することは困難です。
浅野は、横浜の港で行われた進水式のシーンにインバネスを羽織り、山高帽を被った恰幅のよいその姿を現しています。それは『BEAUTIFUL
JAPAN』の中に認められるたった一人の実在の有名人物です。当然、浅野とブロツキーの距離を考えてみました。先ずは浅野総一郎という人物がどのような人物であり、どのような業績を残した人であるか百科事典で調べてみました。
『浅野総一郎(1848-1931)は、越中藪田(現富山県氷見市)に百姓の長子として生まれ、1871年に上京、お茶の水で水売りを初め、竹の皮商から薪炭商へ転じ、コークスの売り込みに成功。渋沢栄一氏の知遇を得、投機商人から産業資本家への道を開き、官営深川セメント製造所を貸与され、84年払い下げを受け、浅野工場(後の浅野セメント)を設立。同郷の安田善次郎氏の援助で96年東洋汽船を創立、太平洋航路を開き、豪華船を就航させたが、第1次大戦後の不況で衰退し、その経営を日本郵船に譲った。1913年には安田氏の協力の下、鶴見・川崎海岸の埋め立てに着手し、16年浅野造船所、18年浅野製鉄所(後に両社とも日本鋼管に吸収合併)を設立するなど、多面的な産業王国を築いた。』 (平凡社の大百科事典より)17)
日本の産業勃興期に彗星のように現れ、財閥を築き、大恐慌にあうと瞬く間に財閥を崩壊させた浅野に関しては、時代を象徴する企業家として、生前から現在までに多角的に分析、研究が行われ、さまざまな著書が出版されています。また、個人的な記録も彼の生前にお二人の子息泰次郎、良三両氏によりまとめられており、随分と詳しく、詳細に渡る記録が残っています。しかし、数多くの企業を興し、またそれより多くの企業の運営に係わった企業家としての浅野の例えば文化活動を行った面までに触れて語られた記録は少なく、今回も大正活映という映画会社との関係を探り出し、そこからブロツキーとのつながりを辿るのに手間取ってしまいました。
浅野総一郎の生い立ちは、ブロツキーのそれほど冒険小説のように起伏に富んでいるとはいえませんが、家の事情により幼少時養子に出されたり、その後養子縁組が解消されたり、22歳で土地の豪農の娘と結婚したにも係わらず経済破綻を来たし、結局一方的に縁組みが解消されたりと、若い時代に不本意な屈辱を味わい、借金を抱えて25歳で徒歩で富山の故郷から上京した折りには殆ど無一文であったばかりでなく、名前を変えて生活をする必要に迫られるほど逼迫した状況にありました。事業家として全くゼロから出発した点において浅野総一郎はブロツキーの経歴と重なるところがあります。
東京に出てきて、直ぐにでも働かなくてはならず、資金も縁故もなかった彼は知り合った人から、「お茶の水の水でも売ったらどうだ。それなら元手は要らないよ。」と勧められて、実際にお茶の水の水を売ることから始めました。現在のお茶の水を流れる汚れきった水を見る身にとっては信じられないような話ですが、本郷湯島台と神田駿河台とを分かつ茗渓または仙台堀と呼ばれた掘割から湧き出る水は、古くからお茶を点てるのに適していると評価されるくらい美味しい水であったそうで、浅野が資本金無しでこの水に砂糖を混ぜて売り歩いたというのは本当のようです。砂糖水売りを出発点に徐々に売り物を変えながら成功してゆく物語は既に出ているさまざまな資料で見ていただくことにして、ここでは後にブロツキーと出会い、共同の仕事として日本紹介映画を製作することになった点について、推測を交えて検証してみたいと思います。
最近まで浅野生前、没後に出版された彼の資料を当たってきて、ブロツキーとの関係が文書記録となっているのは次に示す『キネマ旬報』No.422、1966年9月上旬号に田中純一郎氏が「連載 秘録日本映画」で「ロシヤ人ブロドスキー」と題して詳しく記述されている記事たった一つでした。これは川崎市市民ミュージアム学芸員濱崎好冶氏よりコピーの形で提供されたものです。この文章は執筆者が述べているように浅野の関係者からの伝聞の記録が多く、全てにおいて正しい記述とはいえない点を注意して読むべきでしょうが、貴重な資料であることは間違いがありません。
松竹がキネマ事業に手をつけたというニュースが出てまもなく、船の浅野もキネマにのり出し、谷崎潤一郎が文芸顧問に就任したという新聞記事を見たのが大正9年(1920年)の春で、映画雑誌には早くも男女優募集の広告などがみられた。(中略)船の浅野というのは、郵船の向こうをはった有名な東洋汽船の社長浅野総一郎のことで、その息子良三が大正活映という映画会社を創立し、横浜の山下町に撮影所を設け、外国映画はそれまでの中古品とちがい、アメリカ発売早々のものを輸入、万事新しづくめで、映画界に新風を送りこむというのが、その当時の前評判であった。その大正活映〈大活〉も国活と同じく、大正9年から11年(1920−22年)へかけて僅かの間存在した短命な映画会社であった。(中略)大活の前身は横浜山下町の、元町からちょっと山手へ上がったところに小さなスタジオを持つ東洋フィルム・コンパニーで、その持ち主はロシヤ人ブロドスキーだという。私の手元にある文献によって調べてみると、その経過がつぎのようにわかった。ベンジャミン・ブロドスキーが横浜にスタジオを造ったのは大正5年(1916年)で、はじめは芸者の踊りや風景実写などの短編を撮影して、ブロドスキー自身がこれを持って渡米し、セールスに当たっていた。東洋汽船の浅野良三がブロドスキーを知ったのはこの頃である。浅野は汽船会社の重役で、若い国際人だったから、日本紹介の観光映画や劇映画を大いに製作して、外客誘致と外貨獲得に利用したら妙であろうと考え、東洋フィルムに援助の手をさしのべる決心をした。照明用の水銀ランプや新式の現像タンクを買ったのも浅野であり、当時ハリウッドで早川雪洲やトーマス栗原出演の日本劇がさかんに作られていたので、トーマスを監督にいて横浜で日本劇「成金」や「東洋の夢」をプロデュースしたのも浅野である。「成金」は(中略)英文タイトルを使い、輸出向けに作られたが、大して話題にはならなかったらしい。大正10年(1921年)8月に大活が直営した浅草千代田館でも興行され、キネマ旬報に紹介されている。大正8年(1919年)の春、ブロドスキーはでき上がった「成金」や実写フィルム等多数を携え、トーマスや美術係の尾崎庄太郎を伴い渡米、専ら持参フィルムのセールスに当たり、トーマスと尾崎はハリウッドで映画製作の実際を見学した。トーマスと尾崎が三ヶ月の見学を終わり日本への帰途についたのは4月10日であった。浅野とブロドスキーの提携が改められ、東洋フィルムの建物、器財などを基礎に資本金20万円の大正活映が創立されたのはそれから1年後の大正9年(1920年)4月である。
田中純一郎氏の文章を読む限り誤解しそうですが、実際には当初良三に映画作りのABCを教えたのは映画製作の経験を中国で積んでいたブロツキーだったに違いありません。その後トーマス栗原もこれに加わったのですが、栗原は役者出身であることを考えると撮影、編集などは最初はブロツキーの知識、経験が大いに役立ったものと思われます。また、その後の日本の映画上映館のあり方などを良三を通して実行させたのも、アメリカ時代にさんざん劇場経営で苦労した経験のあるブロツキーだったと思います。
田中順一郎氏は、南部爾太郎氏が『活動画報』1922年10、11,12月号月号に書かれた「キネマ界の解剖記 大活回顧録」を参考に、同時に大正活映の関係者に直接話を聞き、それらを併せて資料にして上記の記事を書かれました。しかし、南部氏の文章は大正活映が松竹キネマと業務提携した直後にショックを感じて書かれたやや客観性を欠いたものであり、伝聞による情報は、こうした情報には常にありがちなあやふやな記憶に基ずいた情報であるので、田中氏の記事にも当然のように不正確であったり誤った表現があることは知っておく必要があるでしょう。ここで述べられている「ロシヤ人ブロドスキー」というのは、『BEAUTIFUL
JAPAN』製作者ブロツキーのことです。ブロツキーは当時米国籍を取得していましたからその点でこの記述は間違いです。
ブロツキーが「スタジオを持ったのは大正6年(1917年)」と記述されていますが、横浜貿易新報の1918年(大正7年)4月3日の記事に「撮影所もほどなく落成したるをもって」とあるところから、翌17年から開始される『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影計画の準備に入り、その後劇映画の製作を計画していたのでスタジオ建設の話は出ていた頃と思いますが、実際にはまだスタジオはできておらず、ここは「ブロツキーは東洋フィルム会社支配人として事務所を横浜に持っていたは大正6年、スタジオを持ったのは大正7年」とすべきであったと思います。
また、南部氏はご存じなかったようですが、当のブロツキーはジャパン・ディレクトリー横浜版18)によると、1913年(大正2年)にヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ社という会社を横浜に興し、同社の総支配人をもって任じていたという記録があり、ブロツキーの日本における人物像を紹介する場合には、遡って「1913年より日本で仕事をしていた」と記すべきではないかと思います。
ジャパン・ディレクトリーというのは、外国人が多く住んでいる東京、横浜、神戸、長崎といった大都市の外国人およびその企業、店舗の住所、電話番号、代表者名等を記述した名簿で、そういった外国人たちの役に立つ日本国の役所、教会といった団体名、連絡先も英語で記され、旧居留地に住む日本人名、日本企業名も記載されていまする。
以下に1912年より1923年までのジャパン・ディレクトリ横浜版に記述されたブロツキーと東洋汽船の浅野総一郎に関係する部分を抜き書きしてみます。実は税関入出国記録を探ろうとしたのですが、残念なことに関東大震災以前の記録は大震災の災害で大部分が焼失し、残ったわずかな書類も第2次世界大戦の戦災で紛失したということでした。またこの時代、外国人の入出国の資料は当時刊行されていた英字新聞の港到着乗船客リストにも記載されていますが、調べてみると到着した船の数のわりに到着リストに載っている人数が余りにも少なく、これが完全な入出国リストとはいえないと判断しました。はたして、このリストにはブロツキーの名前は記載されていません。例えば船会社の関係者として入国したような場合このリストに載らないことが考えられます。
ジャパン・ディレクトリーの横浜版への関連記載事項
1912年 この年、ブロツキーについての記載無し。
Toyo Kisen Kaisha
山下町17
1913年 Variety Film Exchange Co.
山下町72
(American Manufacturers Cinematograph,
Films and Moving Pictures Machines)
B.Brodsky, General Manager
C.H. Pool, Manager
Toyo Kisen Kaisha
山下町17
1914年 Variety Film Exchange Co.
山下町72
(American Manufacturers Cinematograph,
Films and Moving Pictures Machines)
B.Brodsky, General Manager
C.B. Brendoff, Manager
Toyo Kisen Kaisha
山下町75
1915年 Variety Film Exchange Co.
山下町56
(American Manufacturers Cinematograph,
Films and Moving Pictures Machines)
B.Brodsky, General Manager
Toyo Kisen Kaisha
山下町75
1916年 Variety Film Exchange Co.
山下町56
(American Manufacturers Cinematograph,
Films and Moving Pictures Machines)
B.Brodsky, General Manager
Toyo Kisen Kaisha
山下町75
1917年 Toyo Kisen Kaisha
山下町4
1918年 Toyo Film Kaisha 山下町31
B.Brodsky, Manager
(但し、社名、個人名とも索引には不記載)
Toyo Kisen Kaisha
山下町4
1919年 Toyo Film Kaisha 山下町31
B.Brodsky, Manager
(但し、社名、個人名とも索引には不記載)
Toyo Kisen Kaisha
山下町4
1920年 Toyo Film Feature 山下町31
(但し、社名のみ索引に載り、本文住所リストには不記載)
Toyo Kisen Kaisha
山下町5
(但し、索引の住所は4番地のまま)
1921年 Toyo Film Feature 山下町31
(但し、社名のみ索引に載り、本文住所リストには不記載)
Toyo Kisen Kaisha
山下町5
(但し、索引の住所は4番地のまま)
1922年 ブロツキー、東洋フィルム・フィーチャー等の記載は無い
Toyo Kisen Kaisha
山下町5
1923年 Taisho Film Laboratories
山下町31
Toyo Kisen Kaisha
山下町5
現在の山下町31番地には小さなホテルが建っている
1913年にブロツキーが横浜に設けた「ヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ」は、その社名からアメリカ製映画配給と映画上映機材販売会社であったと思われます。横浜の港沿いに広がる旧外国人居留地、山下町の72番地にあり、17番地の東洋汽船本社とは少し離れた位置になっています。1915年(大正4年)、「ヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ」が同町56番地に移り、東洋汽船本社も同年同町75番地に引っ越したことで二社の位置関係はまるで目と鼻の先の距離になりました。
1917年(大正6年)、ブロツキーの会社は本人氏名とともにディレクトリーから消えています。その理由は残念ながら分かりませんが、この一年間に実際は鉄道院の後援で『BEAUTIFUL JAPAN』の撮影が進められたことを考えると大変奇妙な気がします。東京に住所を一時移したかとも思い調べてみましたが、ディレクトリー東京版にもブロツキーに関連した記載はありませんでした。この年、東洋汽船は事務所を山下町4番地に移します。
1918年(大正7年)、ブロツキーの名前が再びディレクトリーに記載されますが、社名は「東洋フィルム会社」と変わり、それまで総支配人(ジェネラル・マネージャー)としていたブロツキーの肩書きは、支配人(マネージャー)となり、住所が同町31番地に移っています。新社名になってもう一つ大きく違っている点は、「ヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ」の場合に「本社は米国、サンフランシスコ」と記載されていた事項が新社の場合は省かれている点です。社名の変更は、ブロツキーの仕事の内容が変化したことを示すと同時に、新社名のネーミングから、この時点で東洋汽船会社の社長であった浅野総一郎との関係が緊密になったことを示しています。事実、雑誌『活動之世界』1918年(大正7年)7月号の記事「同社(東洋フィルム会社)はベンジャミン・ブロドスキー氏及び浅野良三氏共同経営の活動写真撮影専門の株式会社にして、横浜グランドホテルのグランドの一遇に硝子張り撮影場を設立し、近時は、米国より夜間撮影用電気機具一切を取りよせ、大々的に撮影開始すべしと。」とあり、東洋フィルム会社が浅野良三とブロツキーの共同経営であることが明記されていました。
つまり、浅野の資本投入によりブロツキーの日本での活動が、映画配給者から映画製作者に変わったのです。冒頭に『BEAUTIFUL
JAPAN』スミソニアン版にある同作品メインタイトルに「扇子にT.F.K.のマーク」が記されていることを記しましたが、実は浅野家の家紋は扇なのだそうです。例えば浅野造船所のマークは三つの扇子を広げ円にして、扇子にそれぞれCとBとSの字が書かれています。このことから、『BEAUTIFUL
JAPAN』のメインタイトルは、外国人にはブロツキーの作った映像であることが「ベンジャミン・ブロツキー活動写真会社」という社名から分かり、日本人には浅野の後押しでできたことが分かるように工夫されていたのではないかと思うのです。
東洋フィルム会社の事業に関しては、やはり雑誌『活動之世界』1918年(大正7年)1月号で「東洋フィルム会社と称する新会社は、新たに資本を投じ、日本の撮影に米国より監督・技師を来朝せしめ目下九州地方の実景を応用してチャップリン式の日本喜劇を撮影中である」とあります。実際、同社では1917年から18年まで継続して『BEAUTIFUL
JAPAN』の撮影を浅野の資金で行っています。こうした経済的裏づけがあって初めて1917年、ブロツキーは渡米した際にインスの傘下にいたトーマス栗原を始め他の日本人俳優を含む数名のスタッフに翌年から進めようとしていた日本での撮影参加を呼びかけることができたのであり、資金の目処がきちんとしていればこそ、アメリカでの仕事を止めて日本で映画の仕事する俳優・スタッフの動員を成功させることができたのです。
ここで気になるのは「チャップリン式の日本喜劇」という点であり、また「米国から監督・技師を来朝せしめ」という点です。特に監督としては後に1918年4月にトーマス栗原が帰国していますが、雑誌が出版された1月の時点では「米国より来朝した監督」というのはブロツキーをおいていないように思われ、こうした誤解を生みやすい表現が後々の記録に悪影響を与えていると思います。
ジャパン・ディレクトリーは会社の詳細を書いた本文と、索引から成り立っていますが、単なる手続き上のミスかもしれませんが1918、19年の「東洋フィルム会社」の名前は本文には記載されているものの索引には載っていません。
ところで、オーストラリアの研究家フランク・ブレン氏の調査によりますと、サンフランシスコのディレクトリー1917年から1925年にブロツキーの記録が次のように載っているそうです。フランク・ブレン氏は1999年7月にインターネットを通じ私どもの所に連絡がありました。氏はかねがね日本紹介映画に興味をもって調査する内にブロツキーに興味を持ち、スミソニアンHSFAに連絡をしてご覧になったところ、その件ならば既に調査を始めている人間がいると下中記念財団EC日本アーカイブズを紹介されたということでした。
1917年 ヴァン・ネス街840番地
1918年 クレイトン206番地
1919年 サンライズ・フィルム株式会社(ゴールデンゲイト街100番地)
1920年 クレイトン206番地
1921年 サンライズ・フィルム株式会社(ゴールデンゲイト街100番地)支配人
クレイトン206番地(自宅住所)、夫人の名前はマミー
1922年 クレイトン206番地(自宅住所)
1923年 クレイトン206番地(自宅住所)
田中氏が参考にされた南部氏文章「キネマ界の解剖記 大活回顧録」は、1920年8月14日、大正活映と松竹キネマ社の業務提携調印の発表があった直後に、そのことで大きな衝撃を受けられた執筆者南部爾太郎氏により書かれたものです。氏は大正活映が昨日までライバルであった松竹に身売りすることは、それまで大活を精神的に支えてきた全ての人々、大活ファンに対する裏切行為と感じ、「主イエスを売ったユダは?」と疑問を投げかけながら、暗に浅野良三と東洋汽船出身の大正活映重役連の変節振りを責めています。主観的な表現で義憤を込めて綴られている点に留意する必要がありますますが、大活の松竹提携直後に書かれた数少ない資料として今後も使われることを考えると、ここで幾つか間違いを指摘しておきたいと思います。
南部氏が「露國人ボロスキー」としていることは間違えの一つです(田中順一郎氏はこの記事を参考したためブロツキーを「ロシヤ人」と記しました)。南部氏はまた、ブロツキーが日本に最初に設立した会社は『サンライス』であったが、その後『東洋フィルム・コンパニー』と改称したとしています。横浜ディレクトリーと照合すると、この二つの会社名は誤りであり、また「サンライズ」という会社は、むしろ東洋フィルム会社が大正活映に改組された後、ブロツキーが関わったサンフランシスコの映画配給会社として記憶されるべき会社です。南部氏の文章を引用されたその後の数々の資料にクロスチェックすることなく間違えたままこの点が転載されており気になります。
南部氏は大正活映の設立基礎が形成されたのを「1921年(大正9年)1月」としていますが、1917年(大正6年)に浅野の資本投入によりブロツキーとの共同経営という形で東洋フィルム会社が設立され、良三により同社のために照明用水銀ランプや新式の現像タンクなどの機材が買い揃えられており、翌18年には撮影所も新たに建設していたこと、同社が日本紹介映画と2本の劇映画の製作にかかっていたことを考えると、実際には南部氏の記述された年号より以前に基礎はできあがっていたとするべきであろうと思います。南部氏は、大正活映の設立後のブロツキーについて一切触れられていません。しかし、当時の新聞記事によると大正活映はサンライズフィルム社を通してアメリカ製劇映画を輸入し、契約提携映画館でそれらを上映すると記述されており、一方、サンフランシスコのディレクトリーにブロツキーを同地のサンライズフィルム社支配人としているところから、ブロツキーは大活との業務協力体制を保っていたといえます。
南部氏の文章で新たに判明したことは、1920年(大正9年)、浅野良三が資本金20万円を投じ大正活動写真株式会社に改組した点、同社重役3名、志茂成保、小松隆、中谷義一郎(中谷氏は東洋汽船勤務以前、鉄道院の職員でした)が東洋汽船の社員であった点、同社の製作スタッフ構成〔撮影部長:トーマス栗原、顧問:谷崎潤一郎、撮影技師長稲見(TFK)、舞台主任:尾崎(TFK)、映写技師長:松村(國活)、宣伝係:小栗(報知新聞)、説明部:内藤紫漣、白石紫江、杉浦市郎の三氏〕、同社設立趣旨「本邦映画界覚醒のために」、東京有楽座で旗揚げ興行(アメリカ映画『砂漠の情火』、『ピントー』、『踊好きの殿様』、『ゴ社撮影場実況』等。映写機を米国ハウエル社よりシンプレックス電動映写機2台を購入)とその後に行った大阪興行、同年6月から浅草千代田館を封切館とした点、当初から「大活は当年内に50万円を損する」と評された点、大正10年秋130万円の増資が予定されていたにも係わらず浅野系統企業の大整理に遭遇し、敢えなく松竹キネマに身売りという結末を向かえた点等々です。
南部氏、あるいは大正活映をよく知る人たちの文章で気になるのは、新しく作られた映画会社大正活映を社長であった浅野良三個人が興したように記すことです。南部氏の記事でも明白なように、資金・人材は東洋汽船から出ています。この事実は、良三のバックに控える総一郎が当然全てを了承していたことを示しており、そのことは明記すべきであろうと考えます。そして、浅野総一郎を企業家として研究をされる方々にも、今後は浅野の携わった事業の一つとして今まで事業家浅野研究から欠落しがちである大正活映を加えていただきたいと思います。事業家浅野父子が大正活映に東洋汽船から人を差し向け、資本を投じたということは、当然ながらこの二人が東洋汽船側にも利益がある新事業であると認めた上のことであり、従来いろいろの方々により浅野良三が個人の趣味の一線上にこの会社を興したように記すことは間違いであると思います。『活動画報』1921年(大正10年)1月号に片野暁詩氏は「かつて米国にあって俳優生活を送った栗原トーマス氏が、我が実業界の泰斗、浅野総一郎氏の後援を得て大正活映株式会社の創立を発表し…」とこの点を証明するような文章を書かれています。
東洋気船は持ち船、天洋丸、地洋丸、春洋丸といった太平洋航路の客船で乗客のために、ニューヨーク封切りのフィルムを購入し、船内でサービスとして映写をしていました。船旅は長いが故に多用なサービスが求められますが、人手もいらない映画の上映が好評であるとすれば、船会社にとっては好都合です。このサービスが何時から始まったか調べる必要がありますが、この船上映画上映を実現するために、東洋汽船は常に最新の映画情報を入手し、上映映画の上映権を取得し、フィルムの手配をする必要がありました。船の上で映画が乗客に好評であれば、これは陸でも観客に受ける新商売になると東洋汽船関係者が思いついたと考えるのが妥当でしょう。当然、映画配給会社との連携が図られ、映画製作会社にも知り合いができます。ブロツキーのヴァライエティー・フィルム・エクスチェンジ社が東洋フィルム会社に改組された1917年(大正6年)こそ、浅野父子が東洋汽船の利益を考えながら映像製作の業界に足を踏み入れた年といえるでしょう。
浅野総一郎は、長男泰次郎をコンツェルンの中心企業である浅野セメントの後継者とし、次男良三には、彼にとって新しい事業であった船会社、東洋汽船を継がせるためハーヴァード大学に留学させ、国際的企業家に育て上げようとしました。良三は同大学を1912年(明治45年)に卒業し、いったん帰国して東洋汽船に一社員として入社すると再び渡米し、今度はサンフランシスコで実施の研修を受けています。研修の内容は詳しく分かりませんが「はしけ人夫の監督」等と記録にあります。良三がサンフランシスコから横浜に戻ったのは1914年(大正3年)で、以来、良三は東洋汽船で父総一郎の秘書を勤めています。良三がいつ頃、何がきっかけで映画に興味を持つようになったのかそれは現在不明ですが、米国滞在中、例えばサンフランシスコでの研修中にアジアでドキュメンタリーを撮ったことで話題となっているブロツキーの活動について耳にし、実際ブロツキーが撮った中国のドキュメンタリー『A
TRIP THROUGH CHINA』を鑑賞する機会があった可能性はあります。ブロツキーに直接面会した可能性さえあるような気がします。東洋汽船の支社はサンフランシスコの外にも香港、上海、マニラ、ニューヨークとブロツキーが関係していた地点の各所にあり、その上1913年にはブロツキーが横浜に会社を持ったとなると、両者の最初の接触がいつ、どこで出会ったか現在は不明ながら、巾広い可能性があるというわけです。
東洋フィルム会社に関する雑誌記事は幾つか見つかっていますが、その一例を列記してみます。
◇東洋フィルム会社の大発展
東洋フィルム会社と称する新会社は、新たに資本を投じ、日本撮影に
米国より監督・技師を来朝せしめ、目下九州地方の実景を応用してチ
ャップリン式の日本喜劇を撮影中である。近く米国市場に公開される
ことであろう。
−活動之世界 大正7年1月−
その後東洋フィルム会社は事業益々進渉し、最近米国ローサンヂェル
市より、元キーストン会社雇いにして、しばしば本邦の上場映画に現
れし十数名の俳優到着したり。同社はベンジャミン・ブロドスキー氏
および浅野良三氏共同経営の活動写真撮影専門の株式会社にして、横
浜グランドホテルのグランドの一遇に硝子張りの撮影場を設立し、近
時は、米国より夜間撮影用電気器具一切を取りよせ、大々的に撮影を
開始すべしと。
−活動之世界 大正7年7月−
◇「成金」と「東洋の夢」の主役
横浜東洋フィルム会社専属の中島洋好君は、日本チャップリンと称し
ているが、その紛争、表情、仕草は本場の芸風を目の当たりたらしむ
るという。氏は東洋フィルムに2作品「成金」と「東洋の夢」に於い
て主役を演じている。前ニコニコ会の主事として地方興行をしていた
人である。またブロドフスキーとトーマス栗原両氏は右の完成2作品
を持ち、去る11月25日横浜出帆サイベリア丸で渡米した。
−活動之世界 大正8年1月−
総一郎は息子良三を通じてブロツキーにであい、これを支援しようと決めました。それには、息子の判断力を信用していた、期待していた点もありましょうが、それだけでこの現実功利主義の企業家が動く筈がありません。確実な勝算と余程心に響くものがなくてはあり得ないことです。
第一次大戦で東洋汽船は大きな痛手を蒙りました。大戦は当然のことですが人々から旅をする余裕を奪い、東洋汽船から太平洋航路を利用するお客の足を遠のかせたのです。ヨーロッパからの観光客減少は大戦という状況からやむを得ないこととして、当初はまだ参戦していなかったアメリカには日本への旅行は危険ではないのだというような宣伝を行うなど、特別な注目が注がれます。米国からの外客確保は当時の東洋汽船にとってまさに死活問題となり、そのために日本紹介映画を完成させ、それをアメリカ本国で上映することで起死回生が計れるならば、それも良しと総一郎が結論を出したということであろうと考えます。そのような東洋汽船の事情があった上で、大戦直前よりアメリカに起こった日本人排斥運動に対する対策として日本紹介映画製作を行うと決めた官民合同の会議に出席していた総一郎は、率先して映画製作に乗り出し、アイディアとルートを持っていた良三を立てて映画業界に参入したというのが実情なのではないでしょうか。
ともかく、常々語られてきたように単に良三の個人の趣味から浅野が映画業界に参入したわけではありません。しかし、大戦が終わってみると同航路には船が余る状況になり、新型の大型船を他社が用意すれば、東洋汽船はただでさえ減っているお客や荷物を競い合う競争から負ける一方でした。おまけに、日本紹介映画製作は、編集の段階でブロツキーとの間に摩擦を生み、あやうく頓挫しかけ、大正活映が次々に製作した劇映画も利益を生むには至らず、そうこうしている内に東洋汽船の苦境に追い討ちをかけるように1923年9月1日、関東大震災に見舞われ、東洋汽船の屋台骨まで揺るがしました。東洋汽船の維持さえ難しくなったとなれば、いくら良三が頑張って芸術作品の製作紹介に励んでも赤字がかさむばかりの大正活映は結局畳むほかなかったのです。
浅野コンツェルンに関する詳しい資料は多く世に出ているので、浅野総一郎、良三父子についてはそれらを参照していただくとよいのですが、それら資料が殆どの場合「大正活映」を浅野財閥の関連企業に加えていないので、現在「大正活映」について知ろうとする場合、日本映像史、あるいは「大正活映」の文芸顧問を引き受けていた谷崎潤一郎等の線からあたってみる必要があります。しかしそれでも、先に述べたように「大正活映」について書かれた資料にはブロツキーの名前を見つけることは滅多にありません。
浅野総一郎がブロツキー支援に踏み切ったことの心情的な側面を考えてみましょう。先に述べたように、事業を始める段階で二人とも一文無しでした。二人は共通して生育期の教育を満足に受けていません。基本的な教育を身につけていないためにぶち当たる障壁の高さ、厚さを実感した浅野は息子たちには高い教育を受けさせています。立派な後継者に成長した息子たちの存在を誇らしいと感じながら、一面息子たちとの距離も感じることもあったでしょう。その点ブロツキーを身近に感じたかもしれません。ブロツキーは小金を貯めると先ず行ったことはプリンストン大学の教官をお金で買うような形で自分の個人教授にし、英語やその他の知識、アメリカ人としてのエチケットなどを習いました。
浅野は大正8年浅野総合中学校を創設しました。通称浅野学校は浅野グループで働く労働者子弟の教育のためという目的で創られた学校だそうです。事業家として活動を始めてから初めて教育が大切だと知った点において、この二人は共通しています。もう一つの共通点を挙げるとすれば「船」です。ブロツキーが最初に給料を手にしたのは船の下働きでした。それ以来、この時代にすればかなりの距離を船に乗って移動し、そのフットワークの軽さは驚くばかりです。浅野は東洋汽船を起こし、太平洋航路を開き、横浜港建設に力を注きました。二人がどのような会話を交わしたかは不明ですが、年長の浅野がブロツキーの生い立ち、実績、行動半径の広さを知る機会があったとすれば、この年下の青年に親近感を持ち、「これは使いものになるわい」と共同事業者として相手に不足はないと判断する結果を生んだのではないでしょうか。
『BEAUTIFUL JAPAN』に登場する時代の実業家浅野総一郎は、大きなプロジェクトを抱え順風満帆のように一面は見えながら、実は自分の足下では労働争議がおき、新聞沙汰も幾つか起きる等様々な問題を抱える状態にありました。そうした状況の中、ブロツキーの日本紹介映画製作を経済的、人的に支援したことについて、本来はその結果を記録に残すところと思いますが、事業家としても個人としても浅野側としてブロツキーに関する一切の記録・記述がないことは奇異であり、何か意識的なものを感じます。浅野の側でブロツキーと共に映画製作に取り組んだトーマス栗原についても、彼はその後映像製作について多くの文章を発表していながら、ブロツキーに関して触れることはありませんでした。
これは浅野、栗原だけでなくごく身近にいた他の関係者にも共通していえることです。1917年よりブロツキーが撮りためていた『BEAUTIFUL
JAPAN』の素材を使ったと見られるトーマス栗原監督作品『美しき日本』が1920年、大正活映から公開発表されました。この作品は明らかに『BEAUTIFUL
JAPAN』の完成作品版であろうと思いますが、大正活映の記録を書いた人の中にこの作品について書き残している人が見当たらないことも不思議です。日本においてブロツキーに関する記録が極端に少ないのは、こうした意識的抹殺が行われたからであろうと思いながら、結果的に抹殺された理由については現在不明です。
1966年の時点で大正活映の活動について調査された田中純一郎氏は、ブロツキーの存在と、ブロツキーが日本を映像に記録していることまでは掴みながら、ブロツキーの撮影の最終目的が日本紹介映像『BEAUTIFUL
JAPAN』を作ることにあったこと、また日本政府が鉄道院を通じて後援していたこと等の事実は掴まれなかったようです。それは南部氏が「大活回顧録」を書かれた大正11年時点で既にブロツキー情報は極端に押さえて書かれているからでしょう。
浅野個人について記された関連資料として以下の資料を含む数々の著作が出版されています。
奮闘成功録 岩崎錦城 広文堂 大正04年
浅野翁の奮闘史 北村黒風 大成書院 大正06年
浅野総一郎 浅野文庫 大正12年
浅野総一郎伝 北村惣吉 千倉書房 昭和06年
父の抱負 浅野文庫 昭和06年
翁寿像建設経緯 橋本梅太郎 同建設会編 昭和10年
類聚伝記大日本史12 雄山閣 昭和11年
財界巨人伝 河野重吉 ダイヤモンド社 昭和29年
日本財界人物列伝1 青潮出版 昭和38年
政商から財閥へ 楫西光速 筑摩書房 昭和39年
浅野総一郎 河野重吉 ダイヤモンド41-21,26,30,34 昭和28年
浅野総一郎 三鬼陽之助 文芸春秋42-8 昭和39年
浅野総一郎の名誉 建築雑誌6-69 昭和25年
浅野総一郎 日本実業家列伝6 木村 毅 実業之日本
55-6 昭和27年
稼ぐに追いつく貧乏なし 斎藤憲一 東洋経済新報社 平成10年
上記の出版社の中の浅野文庫とは、浅野家で起こした出版社です。氏は実業家として成功した後、自分に決定的に欠けていた教育、文化などの大切さに思いをいたすことが多かったようで、浅野文庫、浅野中学校(1920年設立、神奈川県新子安に浅野学園として現存ク)などを起こし、それまでの業績とは別の方面の働きに努めています。大正13年子安台の校庭の一角に本人全身像の銅像が立てられた時、「ここなら、死んでも俺の庭が見下ろせる」と喜んだそうです。なるほどこの銅像が見下ろす工業地帯になっている埋め立て地は、当時ほとんど浅野の努力で作られた土地でした。
copyright 1999 OKADA Masako, All Rights Reserved
掲載開始 2000.01.11.
TOP PAGE
Beautifu Japan index page
BACK
NEXT